全てかどうかは僕も勉強不足で分かりません。
ただ分子の形を決めているのは電子がどういう形で配置されるかです。H2S、H2Oに関しては、真ん中にあるSまたはO原子に非共有電子対があります。これが分子の形に影響してきます。
高校では全て平面上にあるような感じで教わりますが、実際は分子の形や電子配置は3次元的になります。CH4のメタンという分子の立体構造を調べてもらうと分かりやすいのですが、正四面体型の形で電子が配置されており、Hもそこに結合します。Cには非共有電子対は無く、全ての電子がHと結合するためメタンの立体構造は正四面体となります。
H2S、H2Oに当てはめてみるとHが2つ結合しているだけで2組の非共有電子対が残ります。非共有電子対どうしの反発もありますが、電子配置、結合の位置的に折れ線型になってしまいます。
余談ですが、CO2に関しては真ん中のC原子には非共有電子対がありません。そのため電子の配置の形も変わり、また、非共有電子対どうしの反発も無いため直線型になるということです。
長々とすみません。分かりづらければまた聞いてください。




















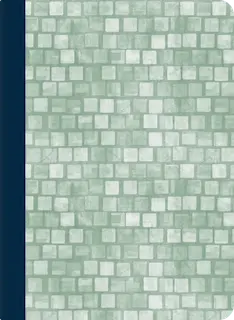






質問者でないものからの質問で申し訳ないのですが
、極性を使ってどのように分子の構造を決定するのでしょうか?
極性はあくまで電子の偏りを見るものだと思っているのですが、、。