✨ ベストアンサー ✨
圧力一定の条件では、PV=nRTにおいてV,nが一定なのでP=kTとなり、圧力は絶対温度に比例することが分かります。
なので定積条件で気体を加熱していくと圧力Pはそれに比例して上昇します。
ただし、水のような揮発性の物質は飽和蒸気圧を考慮しないといけません。実際の水蒸気の分圧の変化を写真に記しておきます。
写真のように最初水蒸気は飽和蒸気圧に従って圧力が増加していきますが、液体の水が全て水蒸気になると、先程説明した圧力が絶対温度に比例する、いわゆる直線のグラフになります。
つまり、沸点はこの飽和蒸気圧に従う区間からPがTに比例する区間に変わる時の温度ということです。
直線、1次関数は2点の座標が求まれば任意の1直線に定まります。
今回は飽和蒸気圧とこの直線の交点(の温度)がまさに求めたいものです。故に直線がどれぐらいの割合で変化するのか、つまり傾きが必要になってきます。
そのため、水をヘリウムや窒素のような不揮発性の気体と考えて、この直線の2点の座標を求めます。
不揮発性の気体は飽和蒸気圧を考えなくてもよいので、どの区間であっても常にPはTに比例する関係が成り立っています。
この考え方を使って60℃、100℃において水が全て気体になっていると仮定して、圧力をそれぞれ求めます。
あとはとった2点を結べば、飽和蒸気圧と交点ができるので、沸点はその時の温度を読み取れば良いです。















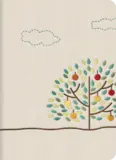






図まで本当にありがとうございます🙇♀️🙇♀️