✨ ベストアンサー ✨
既に回答ずみの方がおっしゃるように、まあ、弱酸に強塩基を入れてるからなんですが...
弱酸+強塩基, 強酸+弱塩基, 弱酸+弱塩基の塩というのは加水分解といって、塩が水と結合して分解する反応が起こります。
なので、できた塩CH₃COONaは加水分解して
CH₃COONa+H₂O→CH₃COOH+OH⁻(可逆反応)
というように、さらに反応が進むんだね。
だからOH⁻が出てきて塩基性溶液になるんだ
違います。
中和点というのと、液性(酸性, 中性, 塩基性)というのは全くの別物です。
中和反応というのは、酸と塩基が出会って塩ができる反応のことですね。
塩というのは塩基の陽イオンと酸の陰イオンが結合して出来た物質になります。
そして、その塩を作ったあとの残りは酸の陽イオンと塩基の陰イオンになりますね。酸の陽イオンとはH⁺のこと、塩基の陰イオンとはOH⁻になりますよね。
中和点とは、この酸と塩基から出されるH⁺とOH⁻の数が等しくなる点のことです。
ですから、結果的にこの時点では全ての反応において中性とみなせるわけです。
しかし、できた塩が加水分解を起こす反応が進行した場合、H⁺やOH⁻が多少できますから液性が変化します。
そのため、今回の中和点においても塩が加水分解するために中性から塩基性に変化したのです。


















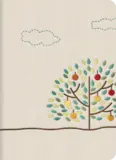






中和点は最終的にその水溶液が何性なのかを表す
ということで合っていますか??
理解力がなくてすみません
良かったら返信お願いします😭🙇🏻