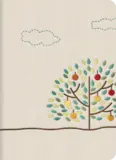✨ ベストアンサー ✨
1. 2枚目の濃度は平行時の話です。3枚目の濃度ははじめの時の話です。平衡時には平衡定数に関わる物質の濃度のバランスで濃度が決定されるので始めや途中がどうだったかは関係ないです。
最初の濃度が変わった影響は全くないのかと言われれば平衡時がc-xとcが絡んでいるため、全く無関係でもないともいえますが、cそのものを平衡定数を考える時に持ってきません。
2. 50ml入れたところで中和されているのが滴定曲線からわかるのでそれまでの段階でH+とOH-が中和されて無くなり、のこりの75-50の15ml分のOH-を考えています。
3.3枚目の蛍光ペンを引いてあるところにあるように酢酸イオンは通常水と加水分解し平衡状態を保つため塩基性を示すようにはたらきますが
外からOH-を加えてやるとルシャトリエの原理に従い平衡が偏ることで、酢酸イオンが加水分解する事は殆どなくなります。そのためエのpHを考える際に酢酸イオンの加水分解によるOH-の出現を考える必要は無く無視できる事を説明しています。