✨ ベストアンサー ✨
ラベルに記載されている値は、質量パーセント濃度です。2〜4までで行なった計算で、りーさんは4.6%という質量パーセント濃度の値を得たのではないでしょうか?(もしこの値に行き着いてないのなら、重ねてご質問下さい。)ラベルに書いている4.2%と比較してみると、実験で得た値の方が少し高くなっていますね。では、これは何故なのか、考察してみたら良いのです。(実は私もこの実験を行なったばかりで、実験値が記載されてる値より大きいことは確認済みなのですが、考察が出来ていません。参考文献かき集めて、調べていきましょっか( ̄▽ ̄*) ・・・ァハハ)
Yahoo知恵袋を漁って私が導いた推論がコチラです(知恵袋などは参考文献に使えるもんじゃありませんが、推測の助け程度にはなるので便利です。)
実験値が高くなるということは、水酸化ナトリウム水溶液の滴定量が過剰だった可能性があります。これは水酸化ナトリウム水溶液が0.100mol/lよりも希薄になっていたからだと考えられます。その原因は、飽和していない水酸化ナトリウム水溶液は、空気中から吸収したCO2から
NaOH+CO2→Na2CO3+H2Oの反応より炭酸ナトリウムを生成して液中に含むというものです。
また、NaOHとNa2CO3は緩衝液を作り、その結果終点が不明瞭となる、のような記述も見かけました。
ありがとうございます。この中和滴定の実験をして
考察や結果を見た上で結論をまとめたいのですが
結論をどのようにまとめるべきかわからず
もしよければ解説教えていただきたいです。
食酢を水酸化ナトリウム水溶液で滴定し、結果として食酢に含まれる酢酸の濃度4.6%という値を得た。この値は食酢のラベルに記載されていた値よりも少し大きく、(考察の要約)ということが考えられた。
くらいでいいと思います。できるだけまとめは簡潔にした方が良いらしいです。
ありがとうございます!レポート無事終了できました。















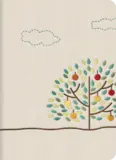






少し高くなっていることは理解できたのですが
それがなぜなのか調べてみたのですがよく分からず…笑