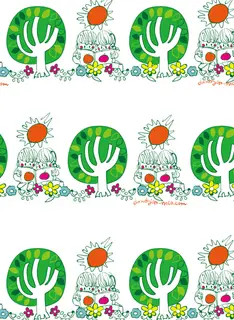生物
高校生
この問題ですが、
採取されたもののうち三齢幼虫に脱皮しつつある二齢幼虫が最も成長の進んでいる個体であり、
表1を参照してどこに該当するかを考えるとほぼ二齢幼虫期の最後までに等しいと考えられ、ADH=h×℃の関係に用いるADHは907.8となる
と考えました。
しかし、解答を見ると、3枚目のようにありました。どうして二齢幼虫期の最終段階までに要するADHが1201.5と考えられるのかわからないので教えていただきたいです。
第2問 次の文章を読み、後の問い (問1~4) に答えよ。 (配点 15 )
完全変態をする昆虫類は卵、幼虫 蛹を経て成虫となる。 幼虫の間にも 脱皮を
行うものでは,脱皮の回数によって、初齢幼虫, 二齢幼虫, 三齢幼虫などの発育段
階に分けられる。
昆虫類は変温動物であり,その発育の進行は外部環境の影響を強く受ける。温
度が高いほど発育の進行は速く、温度が低いほど発育の進行は遅い。そのため、時
間 (h) に温度 (℃) を乗じた積算時度 (ADH, h℃) を尺度に発育をみると,(c) どのよ
うな発育段階についても,そこまで生育するのに要する ADHは一定となる。特定
の発育段階まで達するために必要な時間(h) を ADH から得るためには, ADH を
温度(℃)で割ればよい。 26.7℃の条件でクロキンバエの発生を観察したところ,次
の表1に示す結果が得られた。
発育段階
卵~初齢幼虫
初齢幼虫~二齢幼虫
二齢幼虫~三齢幼虫
表 1
時間 温度
(h)
(°C)
16
26.7
18
26.7
11
26.7
卵からの
積算時度 (ADH)
427.2
907.8
1201.5
問3 下線部(c)に関連して、ADHの概念は,ヒトの死体の死亡推定日時を推定す
る場合に活用されることがある。 野外でヒトの死体が10月15日の午前8時に
発見され,午前9時に警察の鑑識係によってヒトの死体から様々な昆虫が採集
された。その中にクロキンバエの初齢幼虫, 二齢幼虫, 三齢幼虫に脱皮しつつ
ある二齢幼虫は採取されたが, 三齢幼虫は採取されなかった。 また, 死体が発
見された場所における10月11~15日の平均気温を調べたところ、次の表2に
示す結果が得られた。 10月15日の平均気温は午前0~9時の間のデータを示
している。 クロキンバエのADH と表2の平均気温を根拠として,この死体の
死亡推定日時を推定したとき、最も近い日時を、後の①~⑨のうちから一つ
選べ。なお、ヒトが野外で死んだとき、無視できるほどの短時間でクロキンバ
エが産卵すると仮定する。 9
日付
平均気温
(°C)
①
②
10/11
20
10/12
20
表 2
10/11 の午前3時から午前4時
10/11 の午前11時から午前12時
10/11 の午後8時から午後9時
10/12 の午前3時から午前4時
(5) 10/12の午前11時から午前12時
⑥ 10/12 の午後8時から午後9時
10/13の午前3時から午前4時
⑧ 10/13の午前11時から午前12時
⑨ 10/13の午後8時から午後9時
10/13
22
10/14
18
cm 10/15
(午前9時まで)
20
象を春化という。
問3 9 (6)
⑥
採取された幼虫で最も発生が進んでいるものは,
三齢幼虫に脱皮しかけている二齢幼虫、つまり二齢
幼虫の最終段階で,そこまで発生が進むために要す
るADHは表1より1201.5である。
10/15 の午前 9時の時点で幼虫が採取されたが,
この日の平均気温は20℃だったため, 10/15 の
ADH は 9 ×20=180 である。また, 10/14,10/13,
10/12 の 24 時間分の ADHを計算すると, それぞれ
24×18=432,24×22=528,24×20=480 で,
10/13の午前0時~10/15の午前9時までのADH
は 1140 で 1201.5より少なく, 10/12の午前0時~
10/15の午前9時までのADHは1620 で 1201.5を
越えることから,クロキンバエは10/12のいずれか
の時点で発生を開始したと推定される。 ここで,12
日にクロキンバエが発生に要した時間をxとおく
と、次の方程式が成り立つ。
( 9 ×20) + (24 × 18) + (24 × 22) + (x × 20)
1201.5
1
..x=3.075≒3.1 〔時間〕
回答
まだ回答がありません。
疑問は解決しましたか?
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉