ピンクで囲まれた<塩の水溶液の性質>の
4行目、弱酸と強塩基ならなる塩…塩基性
とあります。
つまり、弱酸と強塩基からなる塩は、
酸性塩であっても正塩であっても、すべて塩基性を示すということです。
アは、弱酸と強塩基からなる塩なので、
酸性塩であろうとなかろうと、問答無用で
塩基性を示すということになります。
その通りです。
強酸+強塩基の酸性塩なら酸性と言えます。
では、余談ですが、
弱酸+弱塩基の酸性塩はというと、、
酸性になるとは限りません。
例えば、炭酸水素アンモニウムNH₄HCO₃
は、弱酸と弱塩基からなる酸性塩ですが、
pHは調べたら約8で塩基性になります。
強酸-強塩基だけなぜ酸性塩なら酸性と分かるのか
というと、強酸も強塩基も電離度が1だからです。
弱酸-弱塩基だと双方の電離度の値に応じて、酸性になったり塩基性になったりします。
注意して、ピンクのポイントを間違えないで覚えてください。















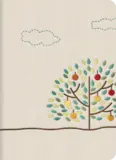






わかりました!
エの場合は両方と強だから何性の塩かを見ればいいってことですか?