✨ ベストアンサー ✨
1計曲線というのは太めの等高線のことです。1/25,000の地形図では10m、20m、30mと10mごとに細めの等高線が入っています。これは主曲線といいます。圧倒的にこの等高線が多いので主曲線と言うのです。全部が主曲線だと1本2本3本4本と数えるのが大変ですので数えやすいので50m、100m、150mと50mごとに太くなっているのです。ですから計曲線といいます。例えば図中のAの左上あたりに・1191とありますね。これは標高点と言ってこの点の位置の標高を表していますこの・のすぐ外側を囲んでいる主曲線は1190mの主曲線です。その外を囲むのが1180m、その外が1170m、その外が1160m、その次が太くなっていて1150mの計曲線です。他にも沢山計曲線があるので全部赤でなぞりましょう。
丁寧に解説ありがとうございます!
助かります!!
2について、まず尾根とか谷とかいう言葉の意味はわかりますか?
私とあなたはともに標高1100mのところに立っているとします。2人の間に尾根があるとお互いが見えません。それが谷だとお互いがよく見えます。つまり尾根とは地形の高まりが細長く続いているもののことで、谷とは低くなったところが細長く続いているところのことです。私の立つところとあなたのたつところとの間に等高線が何本か走っているとします。それが1110mと1120mだとすればあなたは私が見えません。それが1090mと1080mの等高線ならあなたは私が見えます。こうした理屈をしっかり理解した上で次の手順で作業しましょう。
➀地図中で一番高いところを探しましょう。あなたが誤って二番目や三番目のところを一番高いと思っていても別に支障はありませんのでパッと見ぃここが高い!というところに目を付けます。できれば山の頂上のようなところ(等高線が短く、輪っかのように小さく閉じているところ)があればわかりやすいです。
➁その高いところから明らかに下り坂になっている方角を見定めます。➀で選んだところが山の頂上のようなところなら、どちらに向かって進んでも下り坂のはずです。
➂等高線は頂上付近では真ん丸でも、どんどん下っていくと必ずクネクネとカーブします。高いところから低いところに向かう方向に等高線のカーブが低所側に「張り出している」とすればそこは尾根です。高いところから低い方向を見たときに、等高線のカーブが高所側に「入り込んでいる」ならばそれは谷です。
➃どこに尾根があるか見つけることができたら尾根線を書き入れます。等高線の張り出しのピークのところを結んでいきます。何と何を結ぶかというと1200m計曲線のカーブの先っぽ、1190m主曲線のカーブの先っぽ、1180mの先っぽ・・・と進めるところまで結んでいきます。先っぽといってもそんなにとんがっていません。ピンピンにとんがっていたらそれは谷の見間違いでしょう。谷線も要領は同じです。通常は尾根線を実線、谷線は破線で描きますが、ここでは色の指定があるので尾根線は緑色、谷線は茶色の実線ですね。
図中左上の・1199から南方向に下っていきながら見たときには、少なくとも846とある付近までは尾根が続いています。途中で何本も尾根が枝分かれしています。ちなみに尾根は何本も分岐しますし、谷は何本も合流していきます。
(スマホだと拡大できるのかもしれませんが、PCで見ていると地形図が拡大できず細部が見えませんので読み取った数値が違っているかもしれませんのでご理解ください)
3について
集水域とは、字の通りで水を集める範囲のことです。世界中に降った雨がここに集まってくるなんて場所がある訳ないですね。では、ある場所に雨水が流れて集まってくる範囲というものがあるはずなのです。それが集水域です。水は低い方にしか流れませんので、尾根を乗り越えて流れることはありえません。ですから尾根線と谷線が正確に引けるようになると集水域は自然に分かりますが、尾根線谷線が引けないと絶対に集水域は分かりませんので尾根線谷線はめちゃ大事です。滋賀県のほとんどの場所に降った雨は琵琶湖に注ぎます。そして琵琶湖から流出する河川は瀬田川だけで、京都府に入ると宇治川と名を変え、他の河川を合流させて淀川になります。つまり滋賀県に降った雨は全てが早かれ遅かれ淀川を流れて大阪市内にたどり着きます。逆に言うと大阪市を流れる淀川の集水域に滋賀県はすっぽり収まるということです。
さてどうしましょう?尾根線谷線を残すことなく引きまくったら自然と集水域が見えてくるかも知れませんが、集水域を探し出す方法自体を言語化できない面があるので、尾根線谷線を引きまくったところで一度見せて貰うか、集水域を予想するところまで頑張ってみて合ってるかどうか見てあげましょうか?自分で判断して下さい。今日は夜まで時間あるので遠慮せずに私を使って下さい。4、5、6は簡単なので続けて説明していきましょう。
4について
この地形図が見つかりましたので、実物を見ています。先ほど下辻山△1005.1と言っていたのは△1306.1でした。失礼しました。
4はAの標高を読んで、1306.1から引き算するだけですね。・1191にほぼ重なっている主曲線が1190mの等高線です。ここからAまで本数を数えるか、図の左端の方に――1050――と標高を明示した計曲線があるので、Aからの本数を数えやすいところまでたどっていってそこから数えるかしましょう。最悪下辻山の山頂1306.1から本数を数えることでも答えは出せますが沢山数えるのは面倒くさいし、間違えのもとだからAの近くで手がかりを探すのが適当です。気をつけるべきは瀬戸貯水池と陸地の境目は湖岸線ですから等高線として読まないように。それと解答欄を見るとあくまで「約」です。等高線は10m未満は読み取れませんから〇百〇十メートルまででよいです。
5について
定規ではかって、掛け算するだけ。25,000分の1は、実際25,000㎝の長さがあるものを地図では1㎝に描いていますよということですから、逆に地図に3㎝で描かれたものは3×25,000、実際は75,000㎝つまり750mとなります。この地図が縮小印刷されているかもしれないので、その時は右上のスケールを使って計算しなければなりません。
6について
平均勾配は実際のところ登ったり下ったりしていても平均してどのくらいの傾きかというのを特定の区間で産出するものです。
標高差×100/水平距離で計算して、%を付けて下さい。
以上で、全て説明しましたが、納得いかないこと、理解できないことなどあれば何でも聞いてください。
尾根線谷線、集水域は合ってるかどうかまた見ますので別質問ででも挙げて下さいね。
全問解説ありがとうございました!!












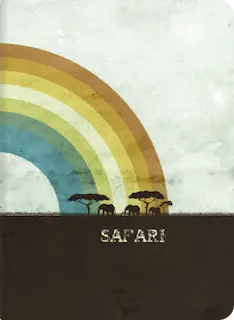




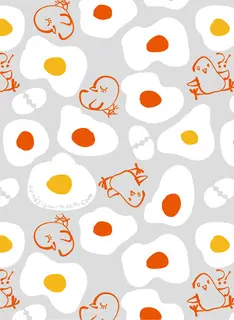






すみません。先ほど・1191から見ていくようにアドバイスしましたが、再度地図を見ると1191は尾根の途中でした。頂上からやった方がわかりやすいので下辻山の△1005.1からやるか、・1191からだと右下に向かって進みながら1190、1180、1170、1170、1160、1150と数えて下さい。先ほどの答えで「囲んでいる」という表現は誤解を招くかと思い訂正します。
2以降はぼちぼち回答していきますので作業しながらお待ちください。