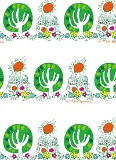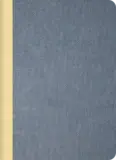暑いと蒸発が促進します。蒸発量が多くなると雲ができやすくなり、降水が生じやすくなります。ですから通常は夏に降水が多くなり、冬は多くありません。暑い寒いの季節がない赤道直下の熱帯では年中降水がみられ、季節風や熱帯偏東風(貿易風)の向きや強さの変化によって雨が多い季節と少ない季節は生じるケースがあります。この問題のFは赤道直下ですからアのグラフになります。
Eは砂漠気候やステップ気候の可能性は捨てきれないとしても地中海性気候かそれに近い気候区であることは難しくありませんね。だって地中海沿岸ですから。それに比べると難しいわけですが、実はGも地中海性気候です。西海洋性気候やステップ気候にも近い性格をもった地中海性気候です。地中海性気候は常識に反して夏が乾季、冬が雨季という珍しい気候です。
この図のEの文字が書かれている辺りは世界最大の砂漠であるサハラ砂漠が広がっていますが、この砂漠の成因は中緯度高圧帯です。一年中下降気流が発達していますので、空気に湿気があっても上空に昇って雲となることが起こりにくくなっています。地球の地軸が公転面に対して傾いていることと関係しますが、北半球が夏の時にもっとも太陽がよくあたるのは赤道直下ではなく赤道よりやや北にずれ、冬の時には赤道よりやや南にずれます。これと同じように中緯度高圧帯も北にずれたり南にずれたりします。高圧帯というように帯には幅があります。サハラ砂漠の中央部は年中中緯度高圧帯の影響下ですが、砂漠の南端北端は季節によっては中緯度高圧帯の影響下からはずれます。
地中海性気候とは、普段は中緯度高圧帯から遠く離れていますが、夏の一瞬この影響下に入ることがあるわけです。ですから常識に反して夏乾季となるのす。冬の降水も多雨と言えるものではなく、普通の冬の雨量です。
さてそういう訳で、EもGも地中海性気候ですが、Eは北半球、Gは南半球ですから季節は逆転していて、7月が夏で乾季になっているイがEで、1月が夏で乾季になっているウがGという答えに至ります。