_①:先ず、「問題文の桁数が2桁の場合、」と有りますが、ぽん さんは、どの値が2桁であると思いましたか?
_②:小学校で、測定は、最小目盛りの1/10 まで読む。と習いましたね。覚えていますか?②、覚えている。覚えていない。を、返信して下さい。
_①〜②を返信して下さい。
_⑤:溶解度とは何ですか?説明して下さい。(溶解度積は高校で習いますが、溶解度は中学で習います。)
_⑥:溶解度と(質量パーセント)濃度との違いと、注意するべきところと、を、説明して下さい。
_⑦『掛け算・割り算の時には、有効桁数の少ない方に、足し算・引き算の時には、有効位の高い方に、合わせて計算します。』→そもそも、このことが分かっていなかった。今回初めて聞いた。と、言う場合は、⑦、有効数字の基礎分かっていません。と、返信して下さい。分かっていれば、⑦、分かってます。と、返信して下さい。
_③〜⑦を返信して下さい。
③確かに、70°Cは計算過程に使っていないですね。
問題文に出てくる数字の桁数が求める答えの桁数を決めるわけではなく、設問の答えを求める計算過程に用いていない数字は考えなくて良いということですよね。
温度(70°C)は離散値ですから、そもそも有効数字という考え方は適用しないんですよね?
④最小目盛は0.0gであっていますか?
⑤溶解度は溶媒(一般に水)100gに溶ける溶質の最大量のことです。
⑥溶解度は水100グラム当たりに溶ける溶質の最大量で、質量パーセント濃度は溶液に対する溶質の割合を%を用いて表したものです。
⑦教科書、参考書に、位取りの最も高い値などとの記載があり、2、3度読みました。
まず位取りの用語の意味がわからず、そこから調べました。
_③-(1):「問題文に出てくる数字の桁数が求める答えの桁数を決めるわけではなく、設問の答えを求める計算過程に用いていない数字は考えなくて良いということですよね。」→その通りです。
_③-(2):「温度(70°C)は離散値」ではありません。温度は連続して変わって行きますよね?測定に使える温度計で測れるか、は、別にして、70.358……[℃] と、無限に刻む事が出来ます。この様な値は、連続値と言います。詰まり、実数の数直線と言う事です。
_個数は、1[個]、2[個]、と、変わって行きますよね?1.5[個相当] はあっても、1.5[個] は、ありえないのです。この様な数値を離散値と言います。
_⑧:温度は、離散値ではなく、連続値である。⑧、分かった。⑧分からない。を、返信して下さい。
_今回は、温度はグラフから読み取ることにしか使っていません。計算ではなく、条件として使っているだけです。グラフではなくて、関数(関係式)で与えられ場合には、温度の有効数字も考慮します。
_⑨:離散値と、連続値と、の、違いが分かりましたか?⑨分かった。⑨分からない。を、返信して下さい。
_ぽん さん外出する、と、言うことなので、ゆっくり書いて行きます。
_読み取りとか、グラフの読み取りとかの考え方ダメです。
_夕方か、夜か、に、チェックして下さい。
_⑦:有効数字と、次元解析(≒単位の考え方)と、に付いては、大学受験レベルならば、以下のウェブ・コンテンツが、良く纏まったいる、と、思いますので、これを参考にして下さい。
_少し足りないところとか、大学学部生レベルでは、ちょっと違う、と、言うところもありますが、それは、後で学び直せば良いです。
https://www.zkai.co.jp/wp-content/uploads/sites/15/2019/11/13151037/bc5a9a50a90050028ef12d4426d5b70f.pdf
_⑤:「溶解度は溶媒(一般に水)100gに溶ける溶質の最大量のことです。」→高校レベルでは○(正解)となるでしょう。
_しかし、より正確には、「〜〜溶質の最大量のグラム数のこと。」です。
_何が違うのか?最大量というと、単位は[g] に成ります。最大量のグラム数というと、数値のことなので単位はなくなります。[ ] です。単位がない物理量のことを無名数と言います。例えば、[個] 等も無名数です。無名数でも、何の数値なのか分かり易くするために、単位自体は付ける事がある。と、言う事です。
_詰まり、無名数とは、次元解析をすると、0 乗になる、と、言う事です。
_この話は、上のウェブ・コンテンツを読んで、考えて見て下さい。
_後で、もう一度触れるかも知れませんが、分からなければ、溶解度は、「〜〜溶質の最大量のグラム数のこと。」と、覚え直して下さい。
_そして、次元の 0 の単位は、無名数と言うことを覚えて下さい。
_⑥-1:知っているかも知れませんが、質量とは、慣性の大きさの物理量です。単位は、[kg] です。重量とは、(主に重力の働きに依って生じる)重さであり、要するに、力の大きさのことです。単位は、[kg重]、或いは、[N](ニュートン)に成ります。
_⑥-1:質量と重量との違いが分かった。分からない。を、返信して下さい。
_⑥-2:両方に皿のある、重りの分銅を片方の皿に載せて試薬を測る場合、質量を測っています。
_デジタル表示の精密秤は、仕組みは、デジタル表示の体重計と同じで、重量を測っています。
_ですから、試薬を上皿天秤式の秤で測って試薬を調整すれば質量パーセント濃度に、デジタル表示の精密秤で測って試薬を調整すれば重量パーセント濃度に、成ります。
_⑥-2、質量パーセント濃度と、重量パーセント濃度と、の、違いが分かった。分からない。を、返信して下さい。
_⑥-3:質量パーセント濃度も、重量パーセント濃度濃度も、無名数です。そして、割合を100倍したことを示す為に、[%] と言う単位を使っています。
_溶解度と、濃度と、で、意識して注意することは、分母が、溶媒の質量か、溶液の質量か、と、言う違いです。
_⑥-4:溶解度の単位ですが、本来は、無名数です。そして、大学受験までは、[g] としても、○(正解)が貰える筈です。しかし、難関校(理系)を受験したり、或いは、大学の学部生となったら[g/100g-H2O] を用いて下さい。溶媒が水ではない場合は、H2Oを置き換えて下さい。相手にわかる様に単位を付けていますが、単位を分母・分子で約分すると、g が消えて無名数になる、と、言う訳です。
_④:さて、添付画像のグラフの縦軸の脚注は、「溶解度」となっており、それに対して、横軸の脚注は、「温度 [℃]」となっています。
_溶解度に単位がないのは、無名数だからです。
_縦軸は、20[g/100g-H2O] 毎に引かれていますよね?(100g-H2Oの横棒は、ダッシュです。引き算の演算符号ではありません。)
_ですから、最小目盛りは、20[g/100g-H2O] です。その 1/10 ですから、2[g/100g-H2O] の細かさで読み取らなければならないのです。
_逆に言うと、1[g/100g-H2O] まで読み取ることは、本来はやってはいけません。
_例えば、60[℃]に於けるKNO3の溶解度を、108[g/100g-H2O] とか、106[g/100g-H2O]とか、読み取ることは出来ますが、
107[g/100g-H2O]とは、読み取ってはいけない、と、言うことです。
_そして、70[℃] のKNO3の溶解度を読み取ると、140[g/100g-H2O] であり、有効桁数は3桁に成ります。
_これは、140[g/100g-H2O]が3桁だから、有効桁数が3桁なのではありません。最小目盛りの 1/10 が、2[g/100g-H2O] だから、有効桁数が3桁なのです。
_仮に、縦軸の最小目盛りが100[g/100g-H2O] 毎にしか振っていなければ、最小目盛りの 1/10 は、10[g/100g-H2O] となり、読み取りが
140[g/100g-H2O] であろうとも、有効桁数は2桁になるのです。
_分からないところは、ありますか?
返信が無いようなので、ベストアンサーには選べません。





















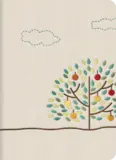






_有効数字とは、有効桁数と、有効位と、で、構成されています。
_掛け算・割り算の時には、有効桁数の少ない方に、足し算・引き算の時には、有効位の高い方に、合わせて計算します。
_有効数字を考えるのは、誤差を含む測定値に関してで、理論的数字やら誤差を含まない離散値、つまり、1[個]、2[個]、と、実際に数えられた離散値(飛び飛びの値)には、有効数字と言う考え方は適用しません。但し、離散値でも、具体的に数えたわけではなく、統計的に求めた数、例えば、アボガドロ数、等に関しては、有効数字を適用します。
_③:さて、有効数字は、計算をする時に、考えるものですね?
_70[℃] は、(2)、の設問を解くときに、計算に用いた値ですか?
_何故、 70[℃] と言う値の桁数が有効数字に関係ないのか分かりましたか?③分かった。③分からない。を、返信して下さい。
_④:設問では、図を測定器の替わりに用いて、KNO3 の溶解度を求めています。ですから、読み取りは、最小目盛りの 1/10 まで読み取らなければなりません。④、縦軸の最小目盛りは、幾つですか?(この様な質問では、当然に単位を添えて回答します。) ④を返信して下さい。
_③④を返信して下さい。