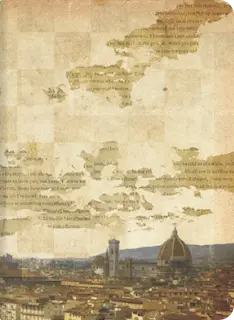生物
高校生
⑵の問題です。解説にあるように図に書いてあることは理解できるのですが、分離比率の意味がいまいちよくわからないのでなぜ答えが0:1:0になるのかがわかりません。なぜ答えがこのようになるのか具体的に回答お願いします。
「基本例題 32 DNAの複製
1953年(ア)と(イ)によりDNAが(ウ)構造をとることが提案され,
世界中の注目を集めた。 この構造を導き出すにあたっては, DNA 中の塩基である
シトシンと(エ)の比率,アデニンと (オ)の比率がいつも1対1であると
いう実験的な成果も参考にされた。 さらに, 彼らは (ウ) 構造から, DNAの複
製が(力)複製であるという仮説を提唱した。 1958年,これを見事に証明した
(キ)と(ク)である。彼らは,大腸菌を窒素の同位体である『N で標識
した(ケ)を含む培地で14世代にわたって培養し,全 DNAの(コ)中に『N
を組み込んだ。その後,この大腸菌を通常の窒素である 'N のみを含む培地で数世
代にわたり培養した。その間,世代ごとに大腸菌から DNA を抽出した。そして,
(サ)溶液中で遠心分離することで密度勾配をつくり,抽出したDNA を,“N の
みを含む DNA (N +14N), 'N と 15Nを両方含む DNA (N+15N), 15N のみを含む
DNA (15N + '5N) に分離し,その比率を比較した。 その結果, DNA は (力)に複
製され,保存的複製および非保存的複製ではないことを明らかにした。 この発見は,
偶然にも大腸菌のDNAがそろって複製するという幸運によって導き出された。
(1) 文中のア〜サに適当な語句を答えよ。
(2) 下線部について 親のDNA を1代目として2代目のLN+1N, 14N + 15N,
15N + 15N の分離比率を答えよ。
(岩手大)
(1) DNAが二重らせん構造をとっていることを提案したのは, ワトソンとクリックである。
その解明には、DNA の相補的塩基対 (AとT, CとG) の証明が大きな決め手となった。
DNAの複製のしくみについては, メセルソンとスタールが窒素の同位体の 'N を用いた
実験で解明した。そのしくみは、DNAの2本鎖がそれぞれ鋳型になり、新しいヌクレオ
チド鎖がそれぞれで合成されて2組の2本鎖ができるというもので、半保存的複製といわ
れる。
(2)この問題は,必ず図を描いて確認しよう。 2代目のDNAでは IN を含む DNA を鋳型
としてN を含む DNAが複製されているので2本ともN + 15N になる。
2代目
- 鋳型
親 (1代目)
15N.
115N
15N
14N
14N
15N
- 鋳型
解答
グアニン オチミン
(1) アイワトソン, クリック (順不同)
ゥ 二重らせん エ
半保存的 キク メセルソン, スタール (順不同) ケ 塩化アンモニウム
塩基サ塩化セシウム
(2) (N+¹4N): (¹4N+¹5N) : (¹5N + ¹5N) = 0: 1:0
11章 遺伝情報の発現 | 207
11章
サ
15%
WIL..
塩化セシウム
2世代目
20000
15NV
15m,
14N
****
回答
まだ回答がありません。
疑問は解決しましたか?
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉