位相がずれている=弱め合う、ではないですよ。
同位相、かつ、経路差が波長の整数倍(半波長の偶数倍)の場合は強め合う
同位相、かつ、経路差が波長の整数倍ではない(半波長の奇数倍)の場合は弱め合う
逆位相、かつ、経路差が波長の整数倍(半波長の偶数倍)の場合は弱め合う
逆位相、かつ、経路差が波長の整数倍ではない(半波長の奇数倍)の場合は強め合う
ですよ。これをまとめると、画像のようになります。
これは、レンズであっても、回折格子であっても、薄膜であっても、くさび形空気層であっても、ニュートンリングであっても、変わりません。変わるのは、経路差の値だけです。
問題によって経路差が2dになったり、dx/lになったり、2dcosθになったりするだけです。
今回は、経路差は2dすなわち、(m+1/2)×(λ/n)であり、
波長はλ/n(半波長はλ/2n)だから、経路差は波長の整数倍ではない(半波長の奇数倍)ですよね。
で、逆位相だから、強め合う。
分からなければ質問してください























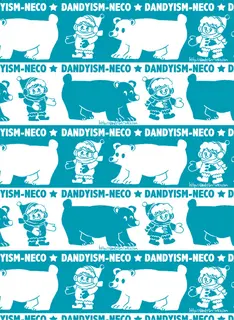





とても分かりやすい説明ありがとうございます!
おかけでしっかりと理解できました🙏🙏🙇♂️