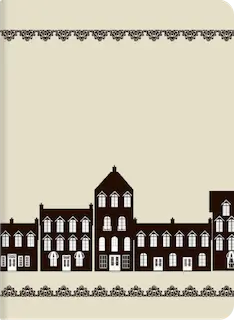✨ ベストアンサー ✨
1段落で商品開発の集団は小規模であることを話題提示し、2段落で小規模である理由説明ですね。
私個人としては、内容を推測しながら読むのはお勧めしません。あくまで文章に書いてあることをそのまま納得する方がいいと思います。というのもこの文章、正直言ってよくわからなくなるほど何か難しいことを言ってるわけでは全くなく、単にあなたが自滅してるだけに思えます。問題を解く上で写真の解説にもあるように表現に着目するのは1つの手です。が、それを文章を読みながらやろうとするとどちらも中途半端になりますし、実際あなたは例示の表現もないのに勝手に具体例を予測してしまってるわけです。
まずは文章を読み筆者の言いたいことを理解すること、その上で問題に取り掛かってください。言いたいことがわかっていれば棒全部の内容説明などが出てもすぐに該当箇所が見つかりますよ。