CからDにかけての輸送には、ATPが必要だとあります。
このことから、CからDへの輸送は「能動輸送」で、濃度勾配に逆らって輸送されると分かります。
よって、濃度はCよりもDの方が大きいと判断できます。
また、DからEへの輸送では、エネルギーは必要ないとあります。
このことから、濃度勾配に従う「受動輸送」が起きていることが分かります。
濃度勾配に従うということから、EよりもDの方が濃度は大きいと判断できます。
これらの条件を満たす式は、(b)と(c)の2つになります。
だから、答えは、③になります。
濃度勾配とは、「濃い・薄いの差」のことです。
濃度勾配に従うということは、濃い方から薄い方に行くということです。
浸透圧は薄い方から濃い方に行くけど、濃度勾配は濃い方から薄い方にいくという考え方で大丈夫ですか?
表現としては大丈夫です。
ただし、浸透圧と濃度勾配では、着目している移動物質が異なりますので、気をつけてください。
浸透圧の場合、着目しているのは水などの「溶媒」です。
こちらは、薄い方から濃い方に移動します。
濃度勾配の場合、着目しているのは塩などの「溶質」です。
こちらは、濃い方から薄い方に移動します。
参考になれば幸いです。
分かりました!丁寧にありがとうございます。













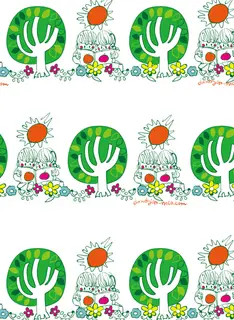








濃度勾配とは濃い方から薄い方にいくということですか?