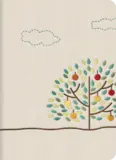化学
高校生
(1)
DE間で起こる現象は沸騰と書いてありますが、なぜ蒸発ではないんでしょうか?
基本例題 4 三態の変化
[温度α [°C] の物質Xの固体を一様に加熱し, d [°C] の気体になるまで
の温度変化を図に示した。
(1) 温度が一定のBC間とDE 間で起こる現象を,
ロ
D
E
それぞれ何というか。
温度
(2) bとcの温度のことを,それぞれ何というか。
[℃]
b
B
C
(3) 物質Xの液体が存在する区間はどこか。
(4) 加熱しているにもかかわらず, BC間とDE間
で温度が上がらないのは,加えた熱がそれぞれ
何に使われているからか。
a A
加熱時間
(5) BC間とDE 間で物質Xが吸収した熱量をそれぞれ何というか。また,どちら
が大きいか。
指針 AB間は固体, CD 間は液体, EF 間は気体であり, BC間では固体と液体, DE 間では
液体と気体が共存している。
一般に,粒子の配列を崩すために必要なエネルギー (融解熱)より, 粒子間の結合を切
るために必要なエネルギー (蒸発熱) のほうが大きい。
解答 (1) BC 間: 融解, DE 間:沸騰
(2) b [°C] 融点, c [°C] : 沸点
(4) BC 間: 粒子の配列を崩すこと DE 間: 粒子間の結合を切ること
(5)BC 間:融解熱, DE 間:蒸発熱。 蒸発熱のほうが大きい。
(3) BE 間
F
他の人はこちらも質問
蒸発と沸騰の違いは何ですか?
蒸発や沸騰は気化の一種である。そして,固体や液体の
表面だけで気化がおこるのが蒸発,液体の内部からでも
気化がおこるのが沸騰である。
回答
疑問は解決しましたか?
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉