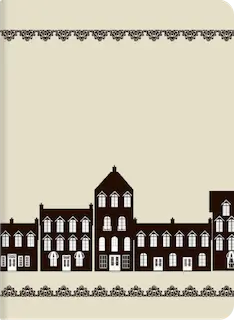現代文
高校生
文章系がほんとにできなくて、、良かったら教えて欲しいです、、
解法テクニック
m P叫エ社
松浦寿輝「小動物のユートピア』
判
展開図
主張の提示一1~3段落
次の文章を読んで、後の設問に答えなさい。
ただしそれは紙型の大小という物理的な問題でもなければ、頁数が厚いか薄いかという大著小著
の差の問題でもない。一冊の書物が「想像的」な対象としてわたしたちの内なる空間に浮上して
くるとき、もしそれを小さなものとして想い描けないかぎり、わたしたちはその書物を本当には一
所有しえないということだ。そして、所有しえない書物とは、結局わたしたちには縁のない書物
のことなのだ。大きな本。それは、わたしたちがいまだ自分の肉体の内に摂り込みかねている本一
筆者の見解
時
書物の魅力は何と言ってもその小ささにある。人が本当に好きになれるのは小さな本だけだ。
書物の魅力はその【小ささ】にある
「想像界」の内で本を【小さくつ ろ一こ
%D
本を【木わう)という行為
のことである。ことは哲学であろうが漫画であろうが変わりない。そして、大きな本が小さくな一
る手応えを味わう瞬間の、何という至福。
「想像界」の内で本を小さくすること。そのために必要なのは本当は、その本を全部読み通す
とか内容を十分に理解するといっただけのことではない。たとえ隅々まで知的に把握しえたとこ 9
ろで大きいままにとどまる書物はいくらもある。わたしたちの肉体が、それを小さなものとして一
受容するという奇蹟が起こらねばならぬ。それがつまりは、愛するということだろう。そしてわ一
一般的な見解(本を愛すること)
。紙型などの【物 」な大小;ものと一
して所有できる書物の【物理】な」
まいに執着すること
II
外見の審美的な鑑賞(4段落)
たしたちが愛せるのは決まって小さなものだけである。こう言ってもいい。愛のただなかでは存一
在も事物も決まって小さくなる。それは、本が物質としてのものでなくなるというのとほとんど
同じことかもしれない。
本を全部読み通すとか内容を十分に理解」
かつう、愛書家とは、ものとして所有できる書物の物質的な位いに執着する人間のことと見な一
するとかいうように【 ん】に理解す
されている。何年に出た第何版という歴史的な出自とともに、装工や紙質や印字の配置といった」
II
内容の知的な理解(4段落)
前段の主張からの発展|4.5段落一
だがわたしたちは、内容の知的な理解からも外見の審美的な鑑賞からも距離をおいたところで」
書物を愛したいと思う。そのとき書物は小さくなる。本当は、大きさ小ささといった物理的範略一
そのものから逸脱してしまうと言ってもよいのだが、ここではあえて「想像的」な比喉としての一
筆者の見解」
愛の対象」
II
||小ささ の利点は何よりも「【憶E]」性
小ささにこだわっておこう。その場合、小ささの利点は何よりもまずその「携帯」性にあるだろ
う。わたしたちはどこにもかしこにも持ち歩ける本を好む。その対極にあるのは、どこか外国の s
図書館にたった一冊しか現存せず、然るべき身元証明を提示し、ややこしい書類手続きを経たう
えでなければ閲覧することのできない稀観本といったもののイメージだろう。おいそれとは近寄一
物理的なもの =小さくてどこへでも持って
行ける(=携帯性)
ることもできないし、ようやくそれに触れる機会にめぐりあっても、うっかりするとたちまち装一
本を愛すること
丁が壊れたり紙葉が制落してしまうので殊の外大切に取り扱わねばならず、そもそも頁をめくる」
のだけでも一仕事であるような、凝りに凝った革装の四つ折り本か何かのイメージ。そうしたも3
のとの出会いが喚ぶであるう感動や興奮も、それなりに理解できないわけではない。だが、小さ
な本の魅力は、そうした厳かに蛇立する不動なもののまとうアウラとは無縁である。それは、近
寄り難いものが人に強いるような敬意を要求することもない。どこへ行こうとそれはいつも人と一
ともにあるからだ。ポケットの中を探ればいつでも指に触れてそれがあることを確かめられるお
守りのようなものなのである。よく懐いた小動物のようにと言ってもよい。ドリトル先生の物語 "
に出てくるあのハッカネズミは、敬愛する先生のくたびれたフラノの上着のだぶだぶのポケット」
にもぐりこんで、どんな遠い旅行にでもついて行くことができたではないか。
だが、繰り返して言っておけば、この小ささは必ずしも物理的なそれではない。物理的に小さ
くてどこへでも持って行ける本の魅力というものはたしかにあるし、ジーンズのポケットにこの一
一冊などと言うとどこかの出版社の文庫本の宣伝惹句みたいになってしまうけれど、岩波文庫の e
小林秀雄訳「地獄の季節」を或る時期肌身離さず持ち歩いていたといった体験に覚えがある人は一
多かろう。あれは菊判の大冊のランボー全集か何かではやはり様にならない振舞いなのである。
II
現実としては書物が一
1である場所
で、書物の内容を一
】の中で一
1思い浮かべられること
一般的な見解」
本を愛すること
厳かに乾立する【不】なもののまとう
アウラ
合
近寄り難いものが人に強いるような
高」を要求する
しかし、本当のことを言えば、ひとたび所有することのできた書物はもはや実際に持ち歩くには一
2 松通寿「小動物のユートヒ
対比設明の
物質的な表情をめぐる趣味階好の洗練が彼の主要な関心事となるだろう。彼は、自分の躯の外に
あるものを愛しているのだ。書物はそのとき、或る確固とした色と大きさと重さと手触りを備え一
ていなければならない
ロ:目
NSUM
mーの
及ばない。人は記憶の中でその書物を、ちょうど鳩の離とか猫の仔とかのように掌の中に暖めな
がら、どこにでも携えて行くことができるのだ。何かを好きだというのは結局そういうことでは 5
ないだろうか。現実としてはそれが不在であるような場所で、それをいかになまなましく思い浮」
かべられるか、という。
主張の裏づけとなる具体例|6段落一
ケネス·グレーアム「たのしい川べ」の内容
II
気候や外敵に脅かされる地上世界とは切り
いまわたしは夏だけ過ごしに来ている外国の町の小さなアパートでこの文章を書いていて、ちょ
うと日本に残してきた自分の猫のことを思い浮かべるのと同じようにして、たとえばケネス·グ
レーアムの「たのしい川ベ」(岩波書店)を思い出してみる。猫を膝の上に抱きかかえてそこに眼 a
を落とすのとちょうど同じような仕方で、あの小動物たちの物語の小さな空間を手と視線で抱擁一
し、記憶の中で慈しんでみる。たとえば、春の陽気に誘われつい聾から這い出してきたモグラが、
川岸でネズミと出会ってそのまま川辺の生活を始めてしまうのだが、やがて或る日遠出の帰りに一
みと自分の旧居のにおいを喚ぎつけ、あちこち捜し回ったあげくようやく探り当てて久々の帰宅一
をすることになるという、あの冬の夜の挿話はどうだろう。玄関の前庭に彫像が置いてある地下 3
の家は、モグラが留守にしていた間にあちこち敵が生えたり挨が積もったりしながらも、しかし」
誰に荒らされることもなく廃屋になることもなく、モグラが出かけた時のままの姿で主人の帰り
を待っていた。大喜びのモグラが友達の川ネズミに家の中を一通り案内しているところへ、仔ネ
ズミたちの唱歌隊がやってくる。折しもクリスマス.ィヴのことだったのだ。川ネズミは仔ネズ」
ミの一人に食べ物やビールやワインを買いにやらせ、やがてみんなでテーブルを囲んで宴会が始 8
まる。この小動物たちの宴はすばらしい。パンやチーズやハムやビールが、これほどおいしそう
離された地中の空間にひっそりと存在する
EEな棲み家
バシュラールの現象学的詩学の補遣として引
かれるにもふさわしい 【心れRt 」のイ
ー×
Léささによって保証されている一
7段落
筆者の考える読書」
「想像界」において、記憶の中の書物内容を、
で見下ろすように、【回性」な関係を
取り結ぶこと
に飲み食いされる場面に小説の中で出喰わすのは滅多にないことで、それも楽しいのだが、何よ一
りも魅力的なのは、気候や外敵に脅かされる地上世界と切り離された地中の空間にこうした安穏
な棲み家がひっそりと存在しているという、バシュラールの現象学的詩学の補遺として引かれる
にもふさわしかろう心地良さのイメージである。そして、この心地良さは、この空間とそこに棲 s
む動物たちの小ささによって保証されているものなのだ。
ほど遠くないところを川が流れていて、そのせせらぎが聞こえてくる野原がどこかにあって、
時
【父篠的】な【a 」の秩序に属す
る説書
そこを冬の真夜中に歩いている自分を想像してみる。そこでふと立ち止まって身をかがめ、足元
の義の下を掘り起こしてみると、地表近くぼっかりあいた空間にモグラと表札のかかった小さな
家があり、暖かそうな黄色い光がぼっと灯ったその小さな食堂では今しも小動物たちの饗宴の真 P
最中で、飲み食いやお喋りに夢中になっている彼らは、窓から覗きこまれているのも気づかずに
ときどきどっと笑い声をあげたりしているのかもしれない。小動物の出てくる物語を読む楽しみ
は、どうやらこの、上から見下ろす視線が内包する特有の心地良さと深い関わりがあるような気
がしてならない。人は、自分に敵意を抱いていない何ものかを上から見下ろし、慈しみの包摂的
なまなざしでもってその小さなものをすっぽりくるみこんでしまうことが好きなのだ。書物とい 花
う、本来は父権的なロゴスの秩序に属しているはずのものに対して、こうした母性的な関係を取
り結ぶことに執着するのはいささか倒錯的と言うべきだろうか。だが読書とは、ただ単に読むこ」
との現在だけを意味しているのだろうか。それはまた同時に、記憶と「想像界」のうちでの抱擁一
のことでもあるのではないだろうか
*限本 = めったに見られない珍しい本。
アウラ=ある人や物の周囲に漂う独特の雰囲気。オーラ。
フラノ=毛織物の一種。フランネル、ネルとも言う。平織りまたは綾織りの両面を起毛した柔らかな紡毛織物。
*惹句=人の注意や興味をひきつける短い文句。キャッチフレーズ。
*菊判 3D書籍の判型の一つ。凝二一八ミリ、横一五二ミリ。
*バシュラール=フランスの哲学者。人間をとりまく空間や物質から喚起させられるイメージをテーマにした物質的想像」
力(詩的想像力)を研究した
*補遺=もれたりした事柄をあとから補うこと。または補ったもの
2 松満寿輝「小動物のユートピア」
® 傍線部「倒錯的」とあるが、筆者の考える読書のあり方が「倒錯的」であるといえるのはなぜか、二百字以内で説明しなさい。
設問チェック]傍線部の「倒錯」という言葉に注目します。「倒錯」とは、「本来存在する秩序に反すること」を意味し、傍線部に含まれる語自体が対比的内容をもっています。
つまり、この問題では、設問そのもので対比関係の説明を要求しているのではなく、言葉によって対比関係の説明を要求しています。
NSUS
mーの
.「筆者の主張」に対応させて、対義的な表現を本文から抜き出したり、自分で考えて補足したりしてみましょう。
一般的なとらえ方=本来のとらえ方」
愛書家は、ものとして所有できる書物の物質的な仲まい
に執着し、自分の堀の外にあるものを愛する
SH@=姫手の事
●型
1ものとして受容する
本を愛するということ」
書物 と父権的な関係を取り結ぶこと
一な関係を取り結ぶことに執着する
苦。
本との関係
(書物は【ロゴス」の秩序に属している)
時
】ものを一
】 視線円
慈しみの包摂的なまなざしでもってその小さなものをすっ
ぼりくるみこんでしまう
ア=D厳かに乾立する不動のもの一
本に向ける視線
)する」
II
懐の中に入れ、その小さなものを上から見下ろす視線
としてとらえる
イ=敬意をもつ
。現実に【所 )する書物について一
。現実としては書物が不在であるような場所で一
。書物の内容を記憶の中でなまなましく思い浮かべられる
内容を
9>
(の声
のー山ロ
Dmーの
GTEP 1) の表を元に下書きをします。
。大切なところを中心に答えを作成していきます。
筆者の主張」と「一般的なとらえ方」を対比的にまとめていきます。
字数が多い場合、省ける言葉や余分な修飾語は削除します。また、字数の多い言葉
ただしここでは、
を同じ内容の短い言葉に言い換えることもあります。
O1般的な見解を基準にして筆者の見解が「倒錯的」だと表現している
「なぜか」と理由を聞いている
ので、文体を次のようにすることが必要です
「本来読書では○○が一般的なのに、筆者は△△に執着するから。」
本来読書では、現実に【広】する書物の内容を一
外見を一
こして、その書物の属している一
の秩序を一
1のものとして畏敬するような一
一な関係を一
取り結ぶのが一般的なのに、筆者は、現実として書物が
】 であ
るような場所でも、書物の内容が記憶の中で一
い浮かべられ、その記憶の内容を自分の懐の中にある一
として見下ろし、
一なまなさしですっぽりくる
みこんでしまうような一
群
一な関係を取り結ぶことに執着するか
松浦寿「小動物のユートピア」
回答
まだ回答がありません。
疑問は解決しましたか?
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉