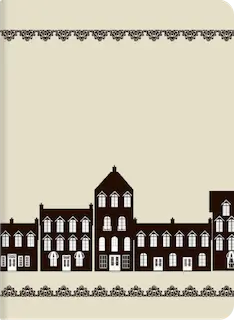現代文
高校生
津村節子さんの絹扇 の1部文です。
最後の四角11は、どういう事ですか?何故武者震いなのか分かりません。
「家事の労働力としてではなく、ずっとしたかった勉強が出来ることに嫌でも気がついたから」と書いて正解でしょうか?
ステップ3
明治時代、貧しい織屋の長女に生まれた但は、傘弟の子守りをし、家業の労働大としてる
た。それでも勉強したいと思ったちよは、両親に頼み込み、やっと宋の弟と一緒に小学校へ通うことが許された。
日太二地当できKト
ミ へ
2背吉たちが、中の中のごぼんさんをして遊んでいる中に入れて貰おうと近づき、「まじってま」と言った。み
なは一瞬困惑の口 を浮かべた。こんな年かさの子と遊んだことはないのである。
3中の中のごぼんさんは、みなで輪になって手をつなぎ、一人がその中にはいってしゃがんで両手で目をふさ
ぐ。周囲の子供たちは、「中の中のごぼんさん、なんで背が低いの。立ってみ、坐ってみ。うしろの正面だあ
れ」と歌いながら廻る。
4輪の中の子供は、それに従って立ったり坐ったりし、輪が止まった時に後ろに誰がいる、と問われて名前を
あてる。あたらなければ、いつまでも中にいなければならない。あたればあてられた子供が代わって中のごぼ
んさんになる。
因ちよは、みなと手をつなぐとイヨウに背が違う。ちよがごぼんさんの真後ろにきた時輪が止まり、すぐ名前
をあてられた。小声で誰かが教えたのである。
心
日ちよは、努力して一年生の遊びにはいっていこうとした。
LO
まわ
まうし
6ちよは早速輪の中にはいることになった。
7中の中のごぼんさん、なんで背が低いの、立ってみ、でちよが立つて、。
一年生の輪の中に突き出るように立っている。
子供たちは面白がって、何度も立ってみ、坐ってみ、を繰り返す。
uそのうち、みな輪を離れてちょ一人を置き去りにしてしまった。周囲が静かになったのでちよが両手をはず
して見ると、滑吉だけが、泣きべそをかいてその場に立っていた。姉がから、
が仲間にはいると、友達との和がくずれるのがつらかったのか。恐らくいずれでもあったのだろう。
的 ちよは、次第に学校へ行く意欲を失っていった。あの五月晴れの日、入学を許されて御院さんにホウコク
しに急いだ時の喜び、石板のはいった風呂敷包みを抱え、田植えの終わったみずみずしい田んぼの中の畔道を、
清吉と並んで学校に向かった日の心のばずみ……
みんなは声をたてて笑った。ちよは、
らかったのか。姉
の
*せきばん
あぜみち
これから、家のためではなく、自分のための勉強が出来る、と武者ど るいのような躯のかるえを感じたものだった。
ロ
回答
まだ回答がありません。
疑問は解決しましたか?
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉