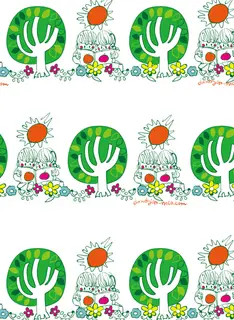質問
大学生・専門学校生・社会人
教員採用試験を来年受けるつもりです。スタートカリキュラムの配慮事項について誤っているものを選ぶという問題なのですが、こういう問題の解き方勉強の仕方がわかりません。よろしければ教えて下さい
3 次の文章は, スタートカリキュラムや, スタートカリキュラムを編成する際の配慮事項について述べたものです。 次の①~
のの中から誤っているものを2つ選び, 番号で答えなさい。ただし, 解答の順序は問いません。解答番号30 31の解答欄にマー
クしなさい。
スタートカリキュラムでは, 小学校への入学当初は, 幼児期の生活に近い活動と児童期の学び方を織り交ぜながら, 幼児期
の豊かな学びと育ちを踏まえて, 児童が主体的に自己を発揮できるようにする場面を意図的につくることが求められる。
の スタートカリキュラムは, 第1学年の生活料における学習の成果が第2学年の生活科にスムーズに接続されるように配慮す
ることをねらいとしていることから, 児童一人一人の思いや願いに合わせた内容の選択や, 学校や地城の実情に合わせた学習
環境の整備などを工夫していくことが大切である。
スタートカリキュラムの工夫の例として, 児童の生活リズムや集中する時間, 意欲の高まりを大切にして, 10分から15分程
度の短い時間を活用して時間割を構成したり, 2時間続きの学習活動を位置付けたりするなどが考えられる。
の 第1学年の児童にとっては, スタートカリキュラムにおいて幼児期の生活に近い活動があったり, 分かりやすく学びやすい
環境の工夫がされていたり、 人と関わる楽しい活動が位置付けられていたりすることが安心につながる。
D スタートカリキュラムにおける指導法の工夫や指導計画の作成方法として, 具体物からの気付きを大切にした学習活動の充
実や, 第3学年以降の総合的な学習の時間における敏材構成の視点を先取りした大単元の設定などが考えられる。
D スタートカリキュラムの編成が必要とされる背景には, 遊びや生活を通して総合的に学んでいく幼児期の教育課程と, 各教
科等の学習内容を系統的に学ぶ等の児童期の教育課程は, 内容や進め方が大きく異なることなどが挙げられる。
の スタートカリキュラムにおける合科的·関連的な指導では, 児童の発達の特性や幼児期からの学びと育ちを踏まえ, 児童の
実態からカリキュラムを編成することが特徴であり, 児童の成長の姿を診断 評価しながら, それらを生かして編成すること
D
D
が求められる。
回答
まだ回答がありません。
疑問は解決しましたか?
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉