✨ ベストアンサー ✨
地震と断層の関係の話です。
地震が起きると断層面に沿って反対向きの力が生じます(図(b)の緑色の矢印)。
このとき、平行逆向きに力が生じ続ける訳ではなく、一点で平行逆向きに力が生じ、その点を中心とした弧状の力が生じるようなイメージです(私の添付した写真の青の矢印のように)。
すると、震央に向かう力の領域と、震央から離れる力の領域が何となくわかります。深奥に向かうのが「引きの地域」、震央から離れるのが「押しの地域」です(押し出される・引っ張られるのイメージ)。
さて、ここまでの説明は、地震が起きたときに震央周辺の地域ではどちら向きの力が生じるか、でした。
これを利用すると「各地点の力の向きを測定すれば震央がわかるのでは…?」と考えられます。
それが表されているのが図(a)です。各地点の向きを測定し、それらを総じた円弧を考えると、2つの円弧ができ、それらが接するのが震央、そして、2つの円弧の境界面が断層面になるということです。
その点についてはあくまでも推定されているだけであって、この図だけではわかりません。引きと押しの各余震の配置から2通りまでは選択肢を減らせますが、それ以上はこの方法だけでは厳密な測定はできません…
(一応、震央思われている点の付近で平行逆向きの余震が確認されれば、それが根拠の1つにはなると思いますが、この図だけでは無理だと思います…)
そうなんですね!ご丁寧にありがとうございました…!ずっと分からなかったので理解できて良かったです🙇♀️


















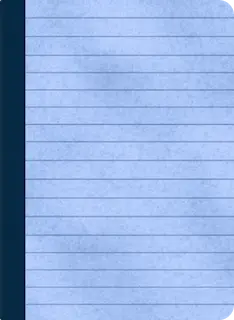





なるほど…だんだん理解してきました…😢
もう1つもし答えて頂けるようでしたらお願いします、「北東ー南西方向の線が震源での断層運動の方向と推定されている」とありますが、なぜその方向だと分かるのでしょうか?