長文失礼します。もっと細かく知りたい場合は参考書や生物学の本を読むことをお勧めします(wikiは細かすぎてあんまり役に立たないです)
呼吸によるグルコースの分解には嫌気呼吸と好気呼吸の2つのメカニズムが存在する。
嫌気呼吸は細胞質基質で行われ、グルコース分解によるエネルギーを利用している生物の全てが行なっている過程である。一方で、好気呼吸はミトコンドリアを持つ生物または好気性細菌が持つエネルギー入手経路である。
どちらも初めは解糖系と呼ばれる、細胞質基質での反応から始まる。この反応はATPを介して行われ、グルコースを様々な酵素を用いることで段階的に分解し、ピルビン酸2分子とATP2分子が生じる。
ここで、嫌気呼吸ではピルビン酸からエタノール(アルコール発酵)や乳酸(乳酸発酵)に分解することでエネルギーを取り出せるが、グルコース1分子あたり2ATPしか取り出せず、効率は非常に悪い。
好気呼吸ではここで生じたピルビン酸が、ミトコンドリア内のマトリックス(内膜の内液部分)でアセチルCoAになったあと、クエン酸回路(クレブス回路とも)に取り込まれて大量の水素イオンを産生する(水素イオンの取り出しにはNADやNADPなどの補酵素が用いられる)。ここではエネルギーは発生しないがピルビン酸の脱水素が起こり、ここで水分子と二酸化炭素分子が生じる(水は後でも生じるが、二酸化炭素が発生するのはクエン酸回路のみ)。
生じた水素イオンはミトコンドリア内膜のクリステと呼ばれる構造に蓄積され、シトクロム複合体やフェレドキシンなどによって電子のポテンシャルエネルギーによって水素イオンの電位の勾配に従って、受動輸送によるATP合成酵素を通過し、酵素の構造が回転することによって発生したエネルギーをATPに貯蓄する。
この時発生した水素イオンはポテンシャルエネルギーに利用された電子と吸気中の酸素と反応して水となり、排出される。この一連の流れを電子伝達系といい、好気呼吸の反応の中で最も多くのATPを合成する。合成量は理論上では36ATPとされているが、厳密には26~28ATPである。
これにより、好気呼吸によるグルコース分解では、グルコース1分子につき理論上38分子のATPが入手できる。エネルギーの抽出率は30%以上にも上り、呼吸は生命活動に必要なエネルギーを得る上で重要な役割を果たしている。
細胞内共生説はマーギュリスが提唱した学説であり、ミトコンドリアと葉緑体は元々別の生物でありそれが共生することで現在の真核細胞が存在するというものである。
主な根拠は2つあり、1つ目はミトコンドリアと葉緑体がそれぞれ二重膜を持つことである。これは、ミトコンドリアと葉緑体のそれぞれの元となった生物(ミトコンドリアは好気性細菌、葉緑体はシアノバクテリアや藍藻が元であるという説が有力)が、真核生物の祖先にファゴサイトーシスによって取り込まれ、外側の膜が真核生物由来、内側の膜が元の生物由来だと考えられるためである。
2つ目は、ミトコンドリアと葉緑体がそれぞれ特有のDNAを保有していることである。とは言ってもこれらのDNAの90%以上は共生の過程により真核生物のDNAに書き換えられているが、残りの数%は固有のDNAを持っており、少なくとも真核生物由来の細胞小器官でないことが窺える。
また、ごく稀に4重膜を持ったミトコンドリアや葉緑体が存在するが、これは共生元の真核生物がさらに上位のユーグレナなどに捕食され、強制的に取り込まれたものであると考えられる(たまに生物の試験にこのネタが出ることがある)。
長文ありがとうございます!!
助かりました!

















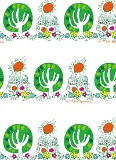





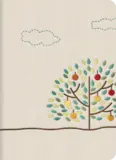



呼吸と燃焼の相違点として、呼吸では様々な種類の酵素による段階的な分解反応によってエネルギーを取り出しているが、燃焼ではグルコース分子が持つ全エネルギーを瞬間的に熱エネルギーに変換していることが挙げられる。
また、呼吸によるエネルギーの吸収率は30%程度でATPなどの化学エネルギーとして貯蓄されるが、燃焼ではグルコースが持つエネルギーの100%が全て熱エネルギーに変換されている。