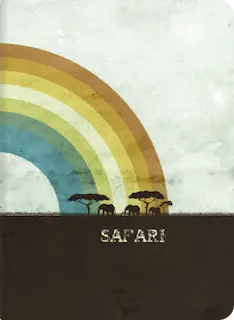26と31は同じ考え方です。子午線1周、赤道1周は約40,000㎞です。これを360°で割り算してやると緯度1°あたり、赤道での経度1°あたりの距離が出ます。緯度や経度というものは地球の中心からの角度のことだということを意識できれば簡単にできるところです。29は経度差を読み取って、赤道での経度1°あたりの距離に掛けてやれば求められます。
25ですが、少し長くなりますが丁寧に説明しておきます。
経線は全て北極点から南極点に至りますからどの経線も同じ長さです。ところが緯線の場合40,000㎞あるのは赤道だけです。南北緯度90度の場合に至っては長さ0です。極点ですからね。地球の断面図と思って円を描いてみてください。そして円を上下に二分する横向きの線分を描きます➀。この線分➀からの角度が緯度になります。線分の中央から北極点に向かう線分を描いたら➁その角は90度ですね。北緯90度=北極点です。では、中央から60度の斜め上に向けて線分を引いてみます➂。円周に達したここが北緯60度です。そこから真下に垂線を降ろします➃。最初に描いた線分➀との角度は90度です。すると1つの角が60度の直角三角形ができました。60度の直角三角形の辺の比は1:2:√3です。習いましたか?この円の「半径」を示す直線が4本出来ましたよね?➀の中央から右側と左側、それと➀の中央から斜め上に伸びる➂の線分、北極点と円の中心を結ぶ➁の4本です。これらの長さは三角比で言うと全て「2」ですね。そして➃の線分は「√3」の長さです。➀と➃の交点から円の中心までの距離が「1」です。ということは赤道は「2」の距離を半径として描いた円であり、北緯60度の緯線は「1」の距離を半径として描いた円になる訳ですよ。赤道1周の距離が40,000㎞なら北緯60度の緯線1周の距離は20,000㎞という訳です。なのにメルカトル図法ではどの緯線も同じ距離に描かれている。引き伸ばされているのです。北緯60度の場合2倍に拡大させて表現されているのです。
地理
高校生
25、26、29、31の計算が何故そうなるのかわかりません。どなたか教えて下さい。お願いします🤲
経線 経線は両極をとおるので大円となる。費線のうち赤道は大円 極に向かうほど紳
科線 線は短くなり, 度代 度線は赤道の2分の1の長さとなる。同一経線上で紳
度 1 度の差は距離にすると約@ kmとなる。
計華 | ロンドン郊外を通る本初子午線が経度 0 度の基準で世界標準時。経度差15度で 1
目 | 時間の時差。
ウインド洋とその周辺の経緯線
右のインド洋周辺の経締線について各問 に | 還
いに答えよ。 [OO年・本, 0年・本改]
" 図のaーeのうち赤道は@ である。
了 カイロ(30N, 31E)
ダッカ(63'N。 90EE)
図の弥作間明は@ 」 度である。
おけるインド洋の東西峠は約@
である。
の大線のうち, 地球上の距離
ダーバン(30*S, 3で)
アリススプリングス(84'8, 184'E)|
回答
疑問は解決しましたか?
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉