✨ ベストアンサー ✨
①地震の震源から角距離103°以上にはS波が伝わらない
②地球の密度が深部ほど大きいことにより、地震波は曲線で伝播するので、103°までの道筋を考えるとこんな感じ
③液体では伝わらないS波が、103°以上に伝わらないことから、液体の領域があるのでは?
→103°に伝わる地震波の曲線を考慮して、青線部の長さを求めると2900km(具体的な計算式は知りません)
2900kmを求める問題は見た事ありませんが、
(1)地震波が真っ直ぐ進むと仮定して外核半径を求めよ
(2)なぜ実際の数値よりも大きくなるのか答えよ
みたいな流れは頻出です。
ちなみに答えは、
(1)添付画像2枚目のような直角三角形を考えることで、
6400cos51.5°≒4000km
(共テならsin51.5°とかtan103°とかのひっかけがあります)
(2)地球の密度は深部ほど大きく、地震波が曲線として伝わるため
みたいな感じです
















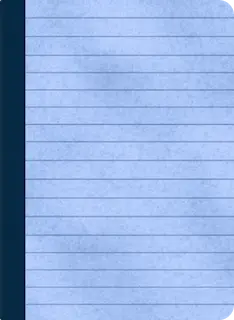





本当に分かりやすいです🥹
頻出問題まで丁寧にありがとうございます🙇🏻♀️🙇🏻♀️