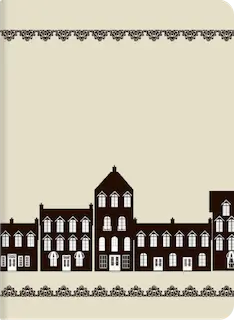現代文
高校生
「いのちは誰のものか?」
1番最後の段落に「いのちの最も基礎的な場面で」とあり、「どのような場面か」という問題が出ました。
どなたかわかる方教えてください🙏🙏🙏
25 いのちは誰のものか?
平侖
わしだ きよかず
いのちは誰のものか?
鷲田清一
からだは誰のものか。いのちは誰のものか。
2
安楽死の問題をめぐって、臓器移植をめぐって、人工中絶や出生前診断の是非をめぐ
って、このことがいつも問題になる。
そのとき、その問いはいつも個人の自由の問題と絡めて論じられる。個人が自由であ
るとは、個人がその存在、その行動のあり方を自らの意志で決定できる状態にあるとい
うことである。わたしの身体もわたしの生命もほかならぬこのわたしのものであって、
この身体を本人の同意なしに他から傷つけられたり、その活動を強制されたりすること
があってはならないというのは、「基本的人権」という理念の核にある考え方であると
いってよい。
3
自殺の正当化にあたっても、献体の登録や臓器の提供にあたっても、その背景にある p
のは同じ論理である。生きて死ぬのはほかならぬこの自分であるから死に方は当人が決
めることができる、自分の身体は自分のものだからそれをどう処分しようと(美容整形
5
安楽死 助かる見込み
のない病人を、本人の
希望に従って、医師が
苦痛の少ない方法で死
なせること。
2 出生前診断 妊婦の血
液検査などによって、
胎児の先天的な異常の
有無を調べる診断。
3 献体 教育・研究目的
の解剖のために、自分
の死後の体を大学など
に無償で提供すること。
是非理念
問題①
当人のもの?そんだけのものでは
問題②
じゃあ
+
自分だけ
評論
27 いのちは誰のものか?
しようと、体内の臓器を他人に譲渡しようと)他人にとやかくいわれる筋合いはない
......というわけである。
他方で、その同じ身体、同じ生命が決して自分だけのものでないことを、わたし
たちは日々痛いほど感じている。人は自分の生命を自分で創り出したわけではないし、
自分の生命を自分で閉じることもできない。誰も自分でへその緒を切ることはできない
し、自分で棺おけの中に入ることもできないとは、しばしばいわれることだ。誰しも他
人の庇護の下で育つ。他人にあれやこれやと世話されながら老いる。
身体や生命を、さらに広く「身」とか「身柄」というふうに取れば、 家族生活を営む
人、いろいろな団体の運営責任を負う公的な立場にいる人にとっては、自分の身体を自
分だけのものだと感じることの方がむしろまれだろう。
このずれはいったい何を意味しているのか。
ここで問題になるのは、冒頭に掲げたような、身体は誰のものか、生命は誰のものか
という問いである。当人のものか、あるいは当人だけのものではないのか、それがいつ
も問われるが、しかしその背後にはさらに、身体や生命はそもそも誰かに所有されるも
のなのだろうかという問題がある。
評論!
西洋の所有論は伝統的に、何かが自分のものであるという所有権の概念を、ものの可
処分性(自分の意のままにしうること)という概念に結びつけて考えてきた。 これはわ
たしのものである、だからこれをどう処分するかはわたしが自由に決めることである、
というわけだ。
この考え方の根にある考え、つまり、この身体はそれを生きているこの自分のも
のだという身体の自己所有権の考えには、ある留保がつけられねばならない。それは、
身体がもしもろもろの物体的対象の一つだとするならば確かにその所有権がうんぬんで
問題である。
きるだろうが、身体そのものははたして所有されるべき物的対象なのだろうか、という
生命についても同様のことがいえる。かつて生物学において、生命活動、特に呼吸が
燃焼の比喩で語りだされたように、生命というと、何か生き物の内部にあって実体のよ
うに存在するものが考えられがちである。 まるで生命の炎とでもいうべきものがあって、
それがいつかふっと消えるかのように、だ。 しかし、生命は他人と共同で維持されるも
のであって、他人との関係から離れて生活というものは成り立たない。食べ物ひとつ調
ライフ
達するのも、社会の大きな機構が働かなくなったら至難のことである。
生命を誰か特定個人の身体のうちに局所づけることはある意味で抽象的なことである。
というのも、身体が純粋に物的な対象として現れるのは、それが他の身体との生きた関
5
10
5
5
◆「ある留保」とは、具
体的にどういうことか
◆「抽象的」とは、ここ
ではどういうことか。
譲渡 庇護 概念 留保
至難
*とやかくいう
*うんぬん(する)
9
28
↓
自分に
評論Ⅰ
係を解除されたときだからである。人の身体と生命は、食や性、育児や介護の場面ひと
つ取ってもわかるように、いつも他の身体との交わりややりとりの中にあるのであって、
特定の身体の座を持つ生命の行く末は、その生命を生きる者、その生命にあずかる人々
のものでもあるのだ。個人のその身体が死体となったとき、その生命をともに生きた者
がその生命を亡きものとして認める、そういう行為をもってやっと一つの生命は終わる
のだ。
5
いのちの最も基礎的な場面で、人は互いのいのちを深く交えている。この交感がいの
ちの中を流れている。
③ 「いのち
からだは誰のものか、いのちは誰のものか。これは、人が誰と生きてきたか、誰とと
もに生きつつあるかという問いとともに問われねばならない問題なのである。
10
な場面」
う場面か
あずかる
回答
まだ回答がありません。
疑問は解決しましたか?
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉