✨ ベストアンサー ✨
なかなか高いレベルを要求されるんですね。ある程度古文に触れてからなら分かりますが、おそらく殆ど初学に近い状態でのテストなんでしょう。
覚え方についてですが、まず、助動詞は接続ごとになんとなくイメージを共有していると思います。
僕が確信してるところで言うと、連用形は「その行いを前提としている」ようなイメージです。もうそれが起こったことは事実と言って過言でないのですから、過去の助動詞や完了の助動詞と相性が良いです。願望の助動詞「たし」は「まほし」よりも強い願望を表します。「たし」は、その内容を事実として扱ってしまいたいほどの思いを持っていることを表す、というように僕はイメージしています。
こんな感じで、他のそれぞれの活用に接続する助動詞群についても、共有するイメージをなんとか見出すことができれば、覚えやすいと思います。
助詞は僕も未だ覚えられていないものも多いと思うので教える立場にあるかは怪しいところですが、例文暗記はすごく効くと思います。助詞は容易にたくさんの種類を付けられますから、助詞をたくさん含んだ例文があれば、それを覚えるだけでだいぶカバーできるはずなので、すごく助けになると思います。
あと、助動詞にも助詞にも共通のこととして、現在も同じ機能で残っている場合があり、そのことを活用できたらした方が良いです。
例えば、現代でも「〜するべき」は、しばしば「〜すべき」という形になっていたりします。「する」の意味と機能で「す」を表すのは、後者は昔の日本語(=古文)の用法が残ったものかなと当たりをつけてみます。古文において「す」はサ行変格活用動詞「す」の終止形です。このことから、「べし」は終止形接続だろうと予想がつきます。
「〜しつつ」は聞きますが、「〜せつつ」は全く聞いたことがありません。同じ「つつ」ですし、明治時代のある時期まで日本語の書き方は古文に近かったので、古文において「〜せつつ」があるなら、僕たちもなんとなくピンとくる可能性が高いと思います。このことから、「〜しつつ」は古文においても「〜しつつ」で、「し」はサ行変格活用動詞「する」の連用形ですから、助詞「つつ」は連用形接続だろうと予想がつきます。
まぁ、現代に残っている助詞は使い方も同じだろうという立場に立ったうえで、パズル的に予想をするということです。ただし、日本語の素養がある程度あることと、動詞の活用を覚えていないと出来ないので、出来る人は限られるかもしれません。
すごく丁寧にありかどうございます!












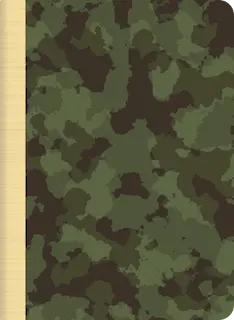



訂正:
段落3
もうそれが起こったことは事実と言って過言でないのですから、
→ それが起こってしまえば、それは事実になりますから、
段落7
「する」の意味と機能で「す」を表すのは、
→ 「する」の意味と機能で「す」を表すことから、