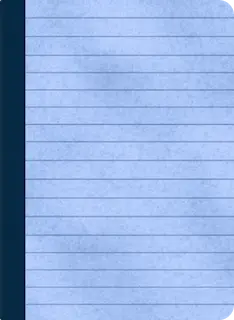cとdの境界で硬くて緻密な組織に変化している=ホルンフェルスが見られるということです。ホルンフェルスは接触変成作用といって貫入したマグマの熱によって変成を受けた岩石となります。もしdよりも先に閃緑岩が堆積したらホルンフェルスは見られません。dが堆積して接触変成作用を受けてホルンフェルスになるのでcの方がdよりあとに堆積したことになるんだと思います。
地学
高校生
どうしてCの閃緑岩がB.Dが形成された後に貫入したと分かるのですか?
1007地層や岩石と地質構造
86. 変成作用を伴う地層の形成過程図1は、ある地点の岩盤を80m 掘削したポーリ
ングの模式的な柱状図を横向きに示したものである。 Aは玄武岩である。 B は灰色の石灰
岩で,Aとの境界付近にはAと同じ玄武岩の礫が含まれており,Cとの境界付近ではよ
り白色で粗粒な組織に変化している。 Cは閃緑岩で,上下の境界面付近では鉱物がより
細粒となっている。Dは砂岩と泥岩の互層で,図2のスケッチに示す構造がみられる。 ま
また, Cとの境界付近では硬くて緻密な組織に変化している。
スケール(1目盛りは10m)
A
B
87. 岩石の循環
D
図 1
(1) 下線部aおよびcの組織の変化によって生じた変成岩の名称をそれぞれ答えよ。
(2) 下線部bの構造が生じた理由として最も適当なものを,次の ① ~ ④ から選べ。
① 中央部よりも急に冷えた
②周囲の岩石の圧力で鉱物が砕かれた
③ 中央部よりもゆっくり冷えた ④ 中央部よりもマグマが貫入する速度が遅かった
(3)(1)の2つの岩石を構成する鉱物に共通する特徴として最も適当なものを次から選べ。
① 鉱物が一定方向に配列している
② 鉱物が白と黒の縞模様をつくっている
③ 鉱物が板状や柱状に薄く変形している ④ 鉱物が方向性をもたない
(4) A~Dを形成順に並べよ。
図
泥岩 砂岩
泥岩砂岩
図2 (地層の向きは図1と同じ)
08.8
(14 宮城教育大改)
80.
解答 (1)(a)結晶質石灰岩(大理石)
(2) (1)
(3) ④
解説 (1) C閃緑岩はB
(c) ホルンフェルス
(4) A→B→D→C
BDはともに接触変成
Dが形成された後に貫入したもので,
作用を受けていると考えられる。
(2) Cが貫入し冷えて固まるとき, 相対的に冷たいBDに触れた部分は,中心部に
比べて急冷されるので鉱物が大きく成長できなかった。
回答
疑問は解決しましたか?
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉