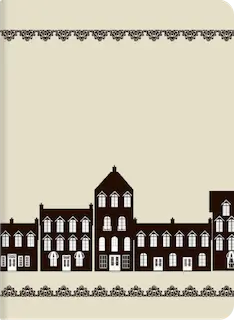現代文
高校生
直後にエの選択肢の"バイアス"という言葉があったので"エ"だと思ったのですがナゼダメで"ウ"になるのですか。
(ニ) つぎの文章を読んで、後の問いに答えよ。
日本の散文芸術(和文体) の歴史を振り返ったとき、厳密な意味での「三人称」の世界が存在したかどうかはきわめて疑わしい。
物語にせよ軍記にせよ、時に現場に密着したある一人の人物から語られているかと思うと、次の瞬間には全体を傍厳する、全一
能的、バノラマ的な視点に切り変わっていたりもする。大宅世継が夏山繁樹に語るのを作者が聞き書きする(「大鏡」)、という
形に象徴されるように、そこでは多くの場合、誰が誰に語るのか、という具体的な「場」が前提となるのであり、たとえ客観的一
0をH6Jき
融通無得な様態を。
の一貫性を求めて無意識のうちに蓋合性をつけて読もうとしているからなのではないだろうか
と感じるのであるとするなら、それはわれわれが近代的な「人称」の概念の影響を受け、視点-
近代以降の小説は、雨洋の十九世紀的なリアリズムを取り込もうとする動きの中で、「人称」という発想に出会い、これを日
本語の言文一致体に実現していこうとする悪載苦闘の歴史でもあった。物語の内容を表現するにあたって、誰が、どのような
資格で語るのか、という問題が、おそらくこれほどまでに厳しく問われた時代はほかにはなかったのである。たとえば一人」
な叙述の形をとっていたとしても、それはあくまでも「よそおわれた三人称」とでもいうべきものなのである。もしもこうした一
64 2014年度 国語
2014年度 国語 63
T日程
大ー
称の視点から語り始めた以上、それが「私」であれ、「予」であれ、「我」であれ、知らないはずのことを勝手に客観することは許
されず、その人物が「いつ」「どこでJ「何のために」語っているのかが常に明らかにされなければならない
たしかにそれは不自由であるのかも知れない。しかしあらゆる時代、あらゆる表現は常に何らかの制約を背負うことをみず
からの宿命としており、制約との戦いなしにはいかなる文学表現も成り立たない。近代小説は、へ称的な「資格」を通して常に
「何を語れぬのか」が問題とされ、かぎられた情報をもとに独自のバイアス||魅力ある空白や矛盾| を生み出してきた歴史
でもあった。
川端康成「雪国」(昭2)の冒頭部分を参照してみることにしよう
国境の長いトンネルを抜けると雪国であつた。夜の底が白くなつた。信号所に汽車が止まつた。
向側の座席から娘が立つて来て、島村の前のガラス窓を落した。雪の冷気が流れこんだ。娘は窓いつぱいに乗り出して
遠くへ叫ぶやうに、
駅長さあん、駅長さあん。」
明りをさげてゆつくり雪を踏んで来た男は、襟巻で鼻の上まで包み、耳に帽子の毛皮を垂れてゐた。
もうそんな寒さかと島村は外を眺めると、鉄道の官舎らしいバラツクが山裾に寒々と散らばつてゐるだけで、雪の色は
そこまで行かぬうちに闇に呑まれてぬた。
の。
冒頭の一文、〈国境の長いトンネルを抜けると雪国
あつた〉の主語は果たして何者なのだろうか
たとえばサイデンステッカーはこの部分を翻訳する際に、The train came out of the long tunnel into the snow
country”とした。天から下界のすべてを見渡す、いわば全能的な視点である。だが、日本語の実感としては、“The train"
を主語にすることには、 この場合かなりのイワ感をともなう。むしろ語りの視点は列車の中にあり、 主人公と共に時間、
t いると考えるペ なので はあるま いか。
九工間
次段落には、娘が列車のガラス窓を落すのを島村自身がまの当たりにする:
法政大- T日程
問三傍線部O「知らないはずのことを勝手に客観することは許されず」とあるが、それはなぜか。その理由として最も適切な
ものをつぎの中から選び、解答欄の記号をマークせよ。
ア西洋の表現技法を取り込んだ近代小説においては、主人公が語る「場」が明示されなければならないから
人称や視点の制約と戦おうとする近代小説においては、厳密な一人称形式は最終的に破綻せざるを得ないから
西洋のリアリズムの影響を受けた近代小説においては、語りや視点の管尾一貫性が保たれるべきであるから
誰が語るのかを厳しく問うた近代小説においては、限られた情報をもとに独自のバイアスがかけられるから。
さ一人称の語り手を設定した小説においては、他者の内面や心情を自由に想像して語ることは許されないから
回答
まだ回答がありません。
疑問は解決しましたか?
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉