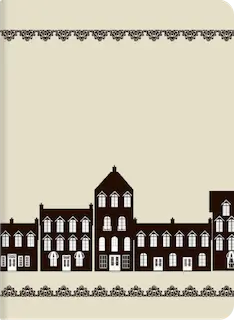解き方の手筋は他の方が示しておられる通りなので、解答に使用する文の探し方についてコメントしておきます。地域柄、上智青学の問題傾向には明るくないので、こちらは学校の先生や過去問を通して確認して下さい。
まず初めに、国語にはある程度の「メタ読み」のスキルが必要です。「受験生・回答者の目線」でなく、「出題者の目線」を持つこと、これは現代文に限らず、他の科目でも役に立ちます。
出題者はまず何も傍線の引いていない文章を読み、その上で自分の感じた「重要らしいポイント」に沿って問題を作成します。また「ここにこう書いてあるから、この部分が答えになる」という明確な根拠を持って問題作成を行います。それを踏まえて、こうした出題者の目線を持って本文を読んでいくと「ここは解答に使えそうだな」とか「離れているけどここも解答に使うんだろうな」といった直感、感覚が身についてくるかなと思います。だいたい、指示語とか接続語とかが根拠・ヒントになります。
質問者さんの心配している「離れたところにポツポツとキーワードがある場合」についてですが、これは出題者としても「難易度は高くなる」と自覚して作問しています。そのため問5など配点が高めの後半に出題してくると思われます。
この時、受験生としては「①それに正面から付き合う」「②軽くいなす」の二通りの選択肢があります。
①ならば頭に入れた本文情報と照らし合わせながら、解答に必要になりそうな離れたキーワードを丁寧に探して出していきます。この方法は、本文を正しく読み込めており、残り時間にも余裕があり、かつある程度の国語力を持った人が可能です。現代文は自分との「相性の良い文章」と「相性の悪い文章」というものがありますから、相性が良くしっかりと読めたと感じたならば、この方法を使っていいと思います。
②については、最初からこの問題で満点など目指さないという態度を持つことです。記述ならば必ず部分点が出ます。適当に傍線前後の情報を集めてきて、組み立てて「回答っぽいもの」を作り、部分点だけを狙います。私は基本的にこの方法を用います。質問者さんの問5の解答がこの方法に近いと思います。時短になり、他の問題の取りこぼしが少なくなります。
最初は②の方針だったけど、近くの情報を漁っているうちに色々と気が付いて、①にシフトしていっても良い訳です。また②の方法に従って部分点を稼ごうと色々書いてたら知らないうちに①になっていた、ということもあります。なので私は記述については②の方針をオススメしますが、質問者さんは既に実践出来ているように見えますので、あとはそこからどうやって①にシフトしていけるか、が課題かなと思います。