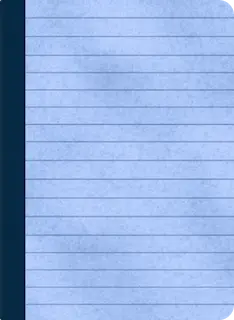Geoscience
มัธยมปลาย
答えがないので間違っていたら正しい解答もお願いします
地球の活動
7
地震の発生と分布
■ 地震と断層
(地震
th
・学習のまとめ
・・・・・・・・
・・・地下の岩石が破壊されることによって、大
地が揺れる現象。
・・・岩石中のある面をはさむ両側が短時間にず
れた変形
(電源
・・・断
面上で岩石の破壊が始まった点。
(震央
活断層地震をおこした断層。 この一部が地表に現
真上の地表の点。
●教科書p.36~37
エート
T練習問題
************
学習日:
月
23.地震断層 次の各文にあてはまるものを,語群から選べ。
(1) ある地震をおこした断層のこと。
(2) 地下の岩石が破壊され、岩石中のある面をはさむ両側が短時間にず
れた変形。
(3)地下で岩石の破壊が始まった。真上の地表の地点。
(4)地震による揺れの強さを示す指標。
日/学習時間
23
分
-0012
(1)地震断層
(2)
(3)震央
れたものを
という。
2度とマグニチュード
(1本
地震波によって発生する揺れ。
(電度
地震動の強さを表す指標 (10段階の震度階級を用いる)。
(フフニチュード) 地震の規模を表す指標。Mが1大きいとエネルギーが10
倍になる。
日本震と余震
という。
大きな地震のあとには、多数の地震がおこる。 このとき、最も大きな地震を("本震
続いておこる地震を (12余震
引き
地震の際に破壊された領域全体を
余の分布を調べることによって,本震の (
4 地震の分布
という。
の形状を把握することができる。
地震は、(プレート
の境界や火山の
分布域に多く見られる。 特に、プレートの
(境界
では、巨大地震を含む多く
の地震が発生し、全世界の地震エネルギーの
が放出されている。
プレートの発散境界やすれ違い境界で発生
する地震は、比較的規模の大きい
)
いものが多い。
深さ 100km よりも深いところで発生する
地震は
とよばれることも
ワーク図中の、 太平洋プレートの境界をなぞれ。
ある。 このような地震の発生は、ほぼ
20
に限られる。
(5) 地震の規模を示す指標。
震度
マグニチュード
(4)
電源
地震断層
震源断層
断層
断層面
(5)
24
24度とマグニチュード 次の各問いに答えよ。
(1) 震度は何段階に区分されているか。
(2)最大の震度はいくらか。
(3) マグニチュードが1大きくなると, エネルギーは何倍になるか。
(4)M7.0 の地震のエネルギーは, M5.0の地震の何倍にあたるか。 次
の ①〜③から選べ
(1) 10
(2) 7
(3)32
① 2倍
知識
② 64倍
1000倍
(4)
->
25.本と余震 次の文の下線部について、正しいものには○を、誤って マグニチュードの
いるものには正しい語句を記入せよ。
(1)地震が発生した際, 最も大きな地震を余震という。
(2)地震の際に破壊された領域全体を震源域という。
(3)余震の数は、時間が経つにつれて増えていく。
(4) 本震の分布を調べることで本震の震源断層の形状を把握できる。
知識
26.地震の分布 次の図は、地震の分布を示している。図に関する以下
の文について,正しいものには○を、誤っているものには×を記入せよ。
(1)地震は、プレートの発散
値が2異なる場合は、 貫
なる場合の2乗になる。
25
まとの3
(1)×
(2)
(3) ◯
(4)×
まとめ
境界よりも収束境界で多く
発生する。
(2)地震は,プレートの中央
部ではあまり発生しない。
(3)大洋底や大陸内部では,
地震は全く発生しない。
(4) プレートのすれ違い境界
26
(1) ×
(2)x
(3)×
(4) O
でも地震が発生している。
思考
説明して
みよう!
地震は、どのような地域で多く発生するか。 25字以内で説明せよ。
➡884
・学習のまとめ・
■ 地震波
地震波には、('P
がある。波の方が(*
め、地震の最初の小さな揺れは波による
ものであり、初期
波と(2)波
いた
S
A-
波到着
動)という。運
れて始まる大きな揺れは主にS波によるも
ので主要動
という。 初期微動が
始まってから、 主要動が始まるまでの時間
初期微動続時間)という。
震源の決定
初期微動
主要動
(P波+S波)
初期微動続時間が長いほど観測地点と震源までの距離は (7長
震源までの距離(km) と初期微動継続時間 T(s) の間には、次のような関係式が成り立つ。
D=kT(k: 6~8km/s) これを(大森公式)という。
初期微動継続時間が15秒のとき, 震源までの距離を求
める。(k=7km/s とする)
(式) D=7×(
きの地震計の記録である。縦軸は揺れの大きさ、横軸は時間を、×印は
地震の発生を示している。 P波の速度を6km/sとして次の各問いに
P.38-39
波到着
練習問題
27. 地震波 次の各問いに答えよ。
学習日:
月
日/学習
分
27
まとめ
(1)①P波
(1)次の①~③の特徴は,主にP波とS波のどちらにあてはまるか答え
よ。
① 観測地点に先に到達する。
② 初期微動を引きおこす。
③ 主要動を引きおこす。
(2) 観測地点にP波が到達してからS波が到達するまでの揺れを何とい
うか。
(3)P波とS波の到着時刻の差を何というか。
知識
28.震源の決定 図は、 同じ地震を異なる観測地点AとBで観測したと
@PIR
• SIE
(2)初期動
(3)
28
と
(1)大森公式
い。震源の浅い地震では、
答えよ。
(1) 観測地点から震源 A
までの距離Dは,
(3)777
D=kT で求められ
る。この関係式の名
称を答えよ。 ただし,
B
kは地域によって決
11秒
(5)
(2)
(3)
(4)
(5)
)
(答) ( 10
)km
B
震源から 84kmの距離にある観測点の初期微動継続
時間を求める。 (k=7km/s とする
(FC) ("
)=7×T
(答) (12
秒
3つ以上の異なる観測地点から震源までのそれぞれの
距離が明らかになれば、各地点からその距離だけ離れた
ところが震源となる。
ワーク 震源までの距離を半径とする円から. 作
図して、 震央を決定せよ。
観測地点A, B.Cの震源距離がわかっているとき.
震源の深さは、以下のように求めることができる。
①観測地点Aから(震央
を含む線の鉛直方向
央
B
(震央距離L
震央
に、震源距離Dを半径とする半円を描く。
②震央から鉛直方向に引いた直線と、半円の交点が
(電源
である。
③震源の深さはAから震央までの距離をLとして
(18三平方の定理)から、D-Lで表される。
震源
思考
説明して
みよう!
震源の浅い地震のまでの距離と初期微動継続時間との関係を、「震源距離」と「初期微動継続
時間」 を用いて,25字以内で説明せよ。
-880-2
まった値をもち, Tは初期微動継続時間(s) である。
(2)k=6km/sとして, Aの震源からの距離を求めよ。
(3)AにP波が到着するのは、地震発生から何秒後か求めよ。
(4) S波の速度を求めよ。
(5)震源から120km離れているBの, 初期微動継続時間を求めよ。
知識
29.震源の決定次の図は,A~Cの各観測地点から震源までの距離を
半径とする円である。 作図によって, 震央に×印を記入し、小数点以下
第一位を四捨五入して震源の深さ(km) を求めよ。 ただし、図の1cmは
10kmを表している。
B
A-
Aを中心とした断面図
地表
A
ヒント AS波は何秒後
に到着するか。
ヒント P波とS波の到着
に要する時間からも求まる
が、大森公式の利用が簡
29
震源の深さ
⇒ まとめ
k
ヒント 源までの距
半径とする円と円の交
直線で結んだ共通弦を
描く。 その交点が震
る。
共通弦
第1回
คำตอบ
ยังไม่มีคำตอบ
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉