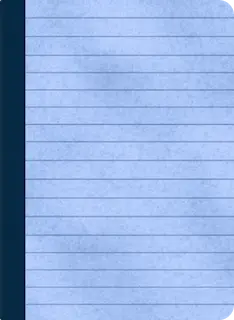Geoscience
มัธยมปลาย
緯度20℃付近で水蒸気圧が2hpa以下で極小となるのが分かりません。
られている。
7
正解は③
6
①正文。大西洋を挟んだ両大陸の海岸線を合わせるとパズルのようによく一致する。
6
②正文。 グロッソプテリス (ペルム紀に繁栄した裸子植物) 等の化石が, 南米南部,
アフリカ南部,南極大陸北部, インド, オーストラリアなどに分布し,これらの
大陸が一つの大陸を形成していたと考えると,その分布の様子を合理的に説明で
きる。
③誤文。 この事実はウェゲナーが大陸移動説を提唱した 1912年当時にはまだ知ら
大気・海洋
れていなかった。 また, これは海洋底が拡大している証拠であって、大陸移動を
直接説明するものではない。
④正文。化石と同様に氷河地形の分布が, パンゲアを考えると合理的に説明できる。
第4問
Aやや難《低緯度の大気の様子》
問 1
正解は ②
①不適。低緯度で水蒸気が多いのは、高温の海水からの蒸発が盛んなためである。
② 適当。 0℃の等温線と2hPa の水蒸気圧を表す破線を見ると、緯度20°付近で水
蒸気圧が2hpa 以下で極小になり、 それより低緯度や高緯度では水蒸気圧が2
hpa より大きくなっている。 同じ温度での相対湿度は水蒸気圧が低いほど小さく
なるので, 水蒸気圧が極小になっているところが相対湿度が極小のところである。
③不適。北緯 70°において, 高度3km では水蒸気圧は1hPaになっている。 相対
湿度は100%を超えていないので、 飽和水蒸気圧は1hPa より大きいことになる。
すなわち, 高度3kmの気温は-20℃より高いことがわかり -20℃の等温線は
高度3km よりも上空にある。
④不適。 図1から赤道付近の気温減率は0.6℃/100m 程度と読みとれる。これは
乾燥断熱減率1℃/100mよりも小さいので、 絶対不安定とはいえない。
8
正解は①
運。積乱雲は大気が不安定になったときに発生する。 大気が不安定になるのは、
くさん含み、上空に寒気が流れ込むなどして気温
次の ① ~ ⑥ のう
動説は、20世
提案するのに
ちから一つ選
と。
的であるこ
まること。
第4問 必答問題
大気と海洋に関する次の問い (A・B)に答えよ。
.
(解答番号
(配点20)
A 低緯度の大気に関する次の文章を読み、 下の問い (問1~4) に答えよ。
次の図1は対流圏における水蒸気圧と温度の分布を示している。 低緯度に水蒸
水蒸気の凝結熱をエネルギー源とするさまざまな現象が見られる。
(a) 積乱雲がよく発
達し、
(b).
また、低緯度ではハドレー循環が卓越している。これに伴って,亜熱帯では晴
気が多く存在していることがわかる。 それゆえ低緯度では,
気圧
天域が広がり, 降水量より蒸発量が多い。 逆に赤道付近では蒸発量より降水量が
多い。この水蒸気の過不足は,ハドレー循環に伴う風によって運ばれる水蒸気に
より補われる。このような赤道付近と亜熱帯における降水量と蒸発量の違いは.
海洋表層の塩分の違いも引き起こす。
水蒸気圧
(hPa)
400
500
600
700
800
900
6
1000
-10
·2·
40°S
2015年度: 地学/本試験 17
20°S
-24-
16 -
-20-
(km)
7
3
2
0
高度
0
20°N 40°N 60°N
緯度
図1 対流圏における水蒸気圧 (破線, 単位は hPa)と温度(実線,単
位は℃) の緯度 (50°S~70°N) ・ 高度分布
~10℃より低い等温線は描いていないが,上空ほどより低温と
っている。
คำตอบ
ยังไม่มีคำตอบ
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉