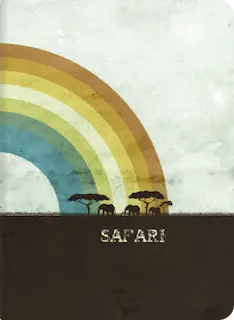都道府県別外国籍人口(絶対値)を日本の白地図を使って階級区分図を作図します。多いところは黒、少ないところは白、多いほど濃くしていきます。すると不都合が感じられることになるでしょう。それは日本人の人口が多いところ東京、神奈川、大阪、愛知は在留外国人も多いですから濃い色になるでしょうね。ところが北海道も濃くなると思うんです。デカいからです。でも北海道に外国人が集中しているとは言えないですよね?その違いが見えなくなってしまうので階級区分図じゃマズい訳です。もちろんこうしたことが起こることを承知の上で作図し、承知の上で読み取るのであれば確かに問題ないといえば問題ありません。でも正解・不正解ではなくブサイクだということなんです。不適切なのです。「神奈川と北海道は同じ色か・・・でも北海道は大きいからなぁ・・・」とか一県ずつ検討するくらいなら、地図化しないで「表」でいいじゃないですか!地図化することの目的はパッとみぃで何か感じられるかどうかというところにあるわけですよ。大ざっぱに見て外国人は大都会に多くてド田舎には少ない。大都市から少し離れた群馬や滋賀は外国人労働者に依存した製造業があるから多いんかなーとかそういうことが読み取れる地図にしないと意味ないわけです。どうしても絶対数にこだわりつつ密度を示すのならドットマップにすることになります。この場合県別データしか入手できなければ叶いません。
普通は県別割合を算出して階級区分図で表現します。人口100人当たりの在留外国人数とかでも不都合は生じません。実数か比率か、それが階級区分図を使用するかどうかのポイントになるわけです。
地理
高校生
地理Bです。絶対分布図と相対分布図の用途を教えてください。
絶対分布図はその地点での数の多さを表しているもの、相対分布図は統計地域ごとの比率や密度を色で分けて表しているものであると理解しています。が
正直どちらも同じような場面で使っても、少し違和感がある程度でどっちを使っても変わらないのではと思ってしまっています。
理解力が低くてすみません、よろしくお願いします。
回答
疑問は解決しましたか?
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉