勉強お疲れ様です(๑•̀ㅁ•́ฅ✧
模試で8割取りたいということなので、まず基本的知識はほぼ完璧に入れておきたいです。
自分の知識の確認のためにセミナーの「プロセス」と「基本例題」を一通り何も見ずにすべて解いてみてください。
全問解ける必要は全くないので分からなかったらすぐ次の問題に行って下さい( ‘-^ )b
答え合わせをすれば自分の知識の漏れが分かります
(どこの分野が苦手とか)(この分野は暗記出来てないとか)
苦手な分野が分かったら重点的にその分野の知識を入れてください
どの問題集をやるにしても、知識が入っていないと意味が無いのでセミナーの「プロセス」と「基本例題」は解いてみてください。
見てみて半分以上解けないようだったら教科書からですがいけると思いますよ( -`ω-)b
あとは知識の入り具合と取りたい点数(記述orマーク)などで解いたらいい問題集も決まってくるので報告待ってます( ’ω’)/
苦手分野でも知識が入ってない場合と問題が解けない場合とがあります。
呼吸となると知識が入ってないように思えます。ふわっと分かるけど流れは説明出来ない感じだと思うので
おすすめは白紙の紙を出してグルコースが解糖系 クエン酸回路 電子伝達系を変化していきながらATPになるまでの過程を書いてみてください
もちろんその時に働く酵素や物質の名前なども書き込んでみてください
そこにかけていることが今定着している知識ということになります。
かけてなかった物質などを教科書を見ながら赤で書き込んで時間を開けて何度かやってれば口で説明できるようになります。
説明できれば一気に流れがわかるようになってくるのでぜひ試してみてください(同化や血液凝固なんかでも使えますよ( -`ω-)b)
ちなみにセンター本番は1ミスの97です
質問あったらしてください✧٩(ˊωˋ*)و✧
盗めるものはしっかり盗んで行ってください( -`ω-)b
質問もガンガンして下さい(๑•̀ㅂ•́)و✧















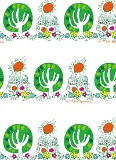



ありがとうございます!、
呼吸のとことか苦手なんですが、苦手分野をどう克服しましたか??
れいさんは、センター何割とりましたか?😊🌟