✨ ベストアンサー ✨
下の図は、教科書に載っている図に少し手を加えました。
夏至のとき、同じ経度のところだと北の方が早く日が当たっていることがわかりますね。北極に近くなると白夜になっています。
同じ経度であれば、北に行くほど早く日が昇ります。
同じ緯度で東に行くほど早く日が昇るのはそうなんですが、あとは、2つの場所の緯度経度がどうなっているかで、どちらが早く日が昇るのかが違ってきます。
冬至の日の日没も同じです。
冬至のところを見ると、同じ経度だと北に行くほど早く夜になっていることがわかりますよね。
日本の北端と東端の緯度経度が、ちょうど夏至の日の出と冬至の日没が、北端の方が早くなる位置にある、というわけです。
















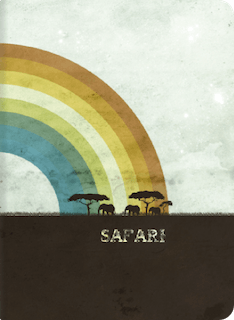





地軸のズレはそんなところにも影響が出るんですね!分かりやすい説明ありがとうございます!分かりやすかったです!