_ユーラシア大陸の南側が、ユーラシア プレートとインド=オーストラリア プレートとの間の狭まる境界、及び、ユーラシア プレートとアラビア プレートとの間の狭まる境界、で、あり、ユーラシア大陸の北側が、ユーラシア プレートと南極 プレートとの間の広がる境界、で、あるからです。
>ユーラシア大陸の北側が、ユーラシア プレートと南極 プレートとの間の広がる境界
南極プレートではなく、北アメリカプレートです。
それから、
>北側には大陸氷河によって地面が削られたため低いのですか?
という質問ですが、
ロシアの西シベリア低地や東ヨーロッパ平原などには、あまり大陸氷河はなかったようです。
だから、氷河による侵食で標高が低くなったというのは、言えないようです。
http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/~syamada/map_syamada/PhysicalGeography/C120522Arctic_icesheet.jpg
_訂正ありがとうございます。助かります。
北部には大陸氷河はなかったのですね。
でも北側は広がる境界があるならば境界の下からマグマが出てきて火山や地震が多いイメージがあるのですが、ユーラシア大陸で火山や地震運動が活発なのはカムチャツカ半島しかなくないですか?
広がる境界があるのにも関わらず標高が相対的に低いのはなぜなんですかね、
広がる境界は陸地ではなくて北極海にあります。
ぺんぎんさんが紹介されたサイトを見ると、どこに広がる境界があるかがわかりますよ。
広がる境界が陸地になっているところは限られていて、アイスランドがよく知られていますよね。
カムチャツカ半島は、狭まる境界が近くにあるために火山活動が活発な地域です。
近くに海溝があって、プレートが沈み込んでいるパターンなので火山も地震も多いです。
_確かに、カムチャッカ半島は、(行ったことはないけれども)火山観光ツアーの宣伝を時々見かけますね。良く爆発しているし。
だとつまり北部の方が西部よりも低平なのは結局なぜなんですかね?
広がる境界は陸地に無いから関係ないですし、。
卓状地が広がっているからというだけで理由になりますか?
西部は造山帯があったりするので標高が高いのは十分理解出来るのですが、
_広がる境界に山・山脈、があっても、左右に引っ張られて、火山のマグマ噴出で高くなった場所がどんどん引っ張られて移動して行くのでそんなに高い山になりません。
_火山があるから標高が高くなるのではなく、狭まる境界だから標高が高くなるのです。
>つまり北部の方が西部よりも低平なのは結局なぜなんですかね?
つまり、標高が高いところは、狭まる境界で、造山運動が現在も起こっているから標高が高いんです。
一方、標高が低いところは、今、造山運動が起こっていない地域で、何億年も昔は造山運動があった地域もありますが、長い間の侵食(おもに雨や川の水によるもの。大陸氷河はほとんどありません)によって削られたために、標高が低くなっています。
卓状地や楯状地も侵食によって低く平らな土地になったものです。
なるほど。
北部は造山運動が長年活発じゃないから標高が高くならず、雨などで侵食されてより標高が低くなっているのですね。わかりました!
ということは、地球上で標高が低い場所は大体は造山運動が活発じゃない場所が多いということですか?だから侵食が進んで、安定陸塊の中で楯状地や卓状地に区分されるのですかね?
_火山活動で標高が高くなるというのもありますせれども、狭まる境界というのは、ベルトコンベアーの様に上手く裏側・下側(詰まり、地殻の下側のマグマ層)へ潜っていくわけではなく、一部が鉋屑(かんなくず)の様に地上に積み上がって行くのです。どんどん積み上がって行くから、高くなるのです。
それは狭まる境界での標高が高くなる要因の一つですか?
_狭まる境界で標高が高くなる主要因です。
_『火山があるから標高が高くなるのではなく、狭まる境界だから標高が高くなるのです。』既に、コメントしています。
そうだったのですか。
自分は狭まる境界で標高が高くなるのは、その周辺は火山が多く、噴火による堆積物等のせいで標高が比較的高くなると思ってましたが、主要因はそうではなく、下へ潜っていくプレートの一部分が鉋屑として積み上がっていくから標高が高くなるということなんですね。
ここまでは授業でも習いませんでした。解説ありがとうございます🙇♀️
_いや、明示的な文では教わっていないのかも知れないけれども、例えば、中学の理科とか、高校の地学基礎とか、で、ヒマラヤ山脈とかモンゴル高原とかで、オウム貝とかの海の生物の化石が見つかっているって、話しを聞いている筈なんだけれども、そこから、鉋屑もどきが積み重なるんだなって、気付かなければならない。
>下へ潜っていくプレートの一部分が鉋屑として積み上がっていくから標高が高くなるということなんですね。
ここまでは授業でも習いませんでした。
教科書にこういう図は載っていませんでしたか?
出典:帝国書院『高等学校 新地理総合』
tkhsreさんは、初めて聞いたみたいに、書いていますが。
確かに狭まる境界に限っては2種類の形があるのは習いました。
そうですか。覚えていてもらえて良かった。
でも、少し前のコメントで
>狭まる境界で標高が高くなるのは、その周辺は火山が多く、噴火による堆積物等のせいで標高が比較的高くなると思ってました
と書いていますよね。
右の図には火山はありません。
ヒマラヤ山脈やチベット高原などは、右の「衝突帯」のパターンなんです。
左の「沈み込み帯」のパターンも、火山から出たものが堆積して山脈になるのではなくて、「衝突帯」と同じ仕組みで山脈や島ができて、そのところどころに火山ができる、という感じです。
沈み込み帯でもプレートが下に沈んでいきますが、いくらから衝突もしているため、衝突帯と同じような流れでその地域の標高が高くなったり火山が出来たりするってことですか?
そう考えていいと思いますよ。
















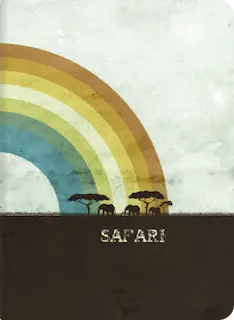





https://y-a.boy.jp/index/2021/04/25/2-3-%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%8B%E3%82%AF%E3%82%B9%EF%BC%88%E5%BA%83%E3%81%8C%E3%82%8B%E5%A2%83%E7%95%8C%EF%BC%89/