✨ ベストアンサー ✨
あってます。
_「局地的大雨が短時間」の短時間とは、数十分、と言う意味です。時間、と言う言葉が使われていますが、1〜2時間と言う意味では有りません。
そんな短いのですね😳
誤認していたようです。
補足説明、ありがとうございます。
_なお、局地的大雨を意味するものとして、ゲリラ豪雨と言う言葉がマス・メディアでしばしば使われます。
_ゲリラとは、元々は小さな戦争と言う意味です。ベトナム戦争の時に頻繁に使われた様です。市民の格好をしていて、森林やら村やらに潜み、何処に隠れているか予想が付かない、その様な現地人から発生する小さな戦いがゲリラ戦、その様な現地人をゲリラ、と呼んでいたのです。
_そして、予測出来なかった局所的大雨を気象庁職員がマス・メディアに説明する時にゲリラ豪雨と言う言葉を初めて使いました。
_気象庁職員は、「予測出来ない局所的大雨」に対してゲリラ豪雨と言う言葉を使ったので、「明日はゲリラ豪雨が予測されます。」と言う使い方は間違った使い方だったのです。
_気象庁の説明会に来ていた某気象会社の社員は、ゲリラ豪雨≒局所的大雨と言う意味で受け取り、気象庁が予測出来ないものを自分達の会社は予測できる、即ち、自分達の会社は優れているので、自分達の会社の予測・解説を買え、とばかりに、民放各社に派遣しているウェザー・キャスター(気象予報士やら、お天気おねえさんやら、)に使わせ捲ったので、ゲリラ豪雨と言う言葉がテレビを始めとするマス・メディアで一気に拡がりました。
_まあ、語源を考えると、ゲリラは単に小さな戦争と言う意味なので、気象会社やらマスメディアやらの使い方がより語源的には相応(ふさわ)しいのかも知れませんけれども。
_元々、使い始めの時には、「予測出来ない」と言う枕詞(まくらことば)があったのです。
マスメディアのゲリラ豪雨とは局地的大雨のことだったのですね
とっても面白いお話ありがとうございました
地理につながる歴史(?)に興味を持つことができました
ご丁寧に本当にありがとうございました












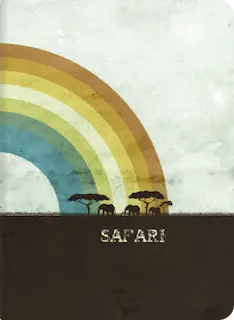





ありがとうございます!