耕地面積率が高い市町村が、1㎢あたりの稲の収穫量が多い傾向がわかります。左の地図で赤く塗られている市町村のうち、2つ以外は右の地図でも赤く塗られていますから。
一方で、耕地面積率が高いのに1㎢あたりの稲の収穫量が高くない市町村もありますね。そういうところは、耕地で稲以外のものを栽培していることが考えられます。
たとえば、深谷市は耕地面積率では最上位のランクの赤になっているのに、1㎢あたりの稲の収穫量は青ですよね。ここは、ネギの産地ですから、畑作が多いために1㎢あたりの稲の収穫量が他の市町村に比べて少ないのではないかなあと思います。
そういうことを書いたらいいのではないかと思いますが、地元の人なら、他にも産地を知っているのではないでしょうか。
でも、600~800字は、ちょっと多いですね。
地理
高校生
新高一で、地理総合についてです。
これは埼玉県の地図なんですが、左の写真が
耕地面積率で、凡例が
40%以上が赤色
30~40%が黄色
20%~30%が緑
10%以下が白色(何も塗っていない)
です。
右の地図が
1k㎡あたりの稲収穫量(t/k㎡)で、凡例が
85以上が赤色
60~85が黄色
35~60が緑
10~35が青
10以下が白色(何も塗っていない)
です。
完成した2枚の階級区分図を比較し、2つのデータの関係性を600字~800字程度でまとめて提出しなければならないらしいのですが、どんなことを書けばいいのか分かりません。
どんなことが読み取れますか?どんなことを書けばいいか教えていただけると嬉しいです、、
塗り方も汚くてとても分かりずらいと思うのですがお願いします、、
TW-4
15-44-88
n-35 A
WEB
回答
疑問は解決しましたか?
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉













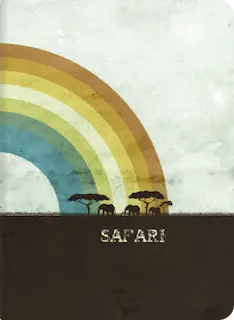





回答してもう1週間以上になりますが、読んでもらえたかなぁ…。