このノートについて
数値解析は微分方程式で表された物理量を、ほぼ解くための手段!
その「ほぼ」ってところをいかにそれらしく解いていくかが鍵となります(偉そう)(むずそう)
非常〜〜に抽象的な話が多く、それ数学的にいいの?ってなる人(俺)にはよく詰まるものです。
頑張っていこう。

他の検索結果
おすすめノート
このノートに関連する質問
大学生・専門学校生・社会人
数学
理統計学の質問です。 問題が分からなくて分かる方教えていただきたいです。
大学生・専門学校生・社会人
数学
数理統計学の質問です。 問題が分からなくて質問します。
大学生・専門学校生・社会人
数学
この問題がわからないです。 数理統計学の単回帰分析の問題です。
大学生・専門学校生・社会人
数学
最小二乗法を用いることは分かるのですが、そこから全く分からないので教えて頂けると助かります……! どなたかよろしくお願いします
大学生・専門学校生・社会人
数学
浮動小数点数の問題です。 問題8を考えているのですが、「負の最大べき乗」 の意味がよく分かっていません。 (-∞)乗 のことでしょうか? 回答よろしくお願いします。
大学生・専門学校生・社会人
数学
回帰係数a,bが求められません😵 解説お願いいたします
大学生・専門学校生・社会人
数学
常微分方程式を有限差分を用いて解く方法を何か例題(解析の条件を与え)を用いて教えてください。 2つくらいあると助かります
大学生・専門学校生・社会人
数学
これも全部わかりました
大学生・専門学校生・社会人
数学
1.2.3全て解けました! 同じ問題解いててわからないって人もしいたら言ってくださーい!
大学生・専門学校生・社会人
数学
統計学の偏相関係数について自分の解釈があっているかの確認をしたいのですが、 こればかりは自力ではできないので確認をお願いしたいです。 (画像は参考にした教科書の内容です。ファイルサイズの問題で必要な情報をすべては載せられませんが一応貼ります。) この教科書の内容は ある人の数学のテストの点(y)に他の科目の点(それぞれx1、x2、x3とする)が線形的に影響を与えるとして、 y=a0+a1*x1+a2*x2+a3*x3+誤差eという関係が成り立つと仮定する。 テストのデータが20人分あるとして、20人分のeの二乗和が小さくなるようなa0~a3を最小二乗法で計算してx1~x3でyを予測するような回帰モデルを考えるという話がメインとなります。 ここからが解釈に不安があります。 教科書には 次にx1を抜いたx2、x3でy、x1を予測する回帰モデルを考えるとき x2、x3で予測されるy、x1の値をy、x1の実測値から引いたy、x1の「予測誤差」をu、vとする。 このuとvの相関係数rは偏相関係数とよばれる。 というように書いてあるのですが、 予測されるy、x1の値を実測値から引いた作業は 「y、x1に共通して影響を与えそうな因子がy、x1に与えていると予測される影響力」を実測値から引き、共通点を減らした実測値の相関関係を見ることで 他の因子の影響が無くなったyとx1のデータには相関関係があるのかを調べることができる。 と自分は解釈しました。 しかしこの解釈の中でも説明しきれない部分があります。 「x2、x3の影響」がなぜ予測値と同じになるのかという点です。 以上の計算式の意味の解釈があっているかの確認。 自分では説明できない点の説明をしていただきたいです。 ご助力ください。よろしくお願いします🙇
News









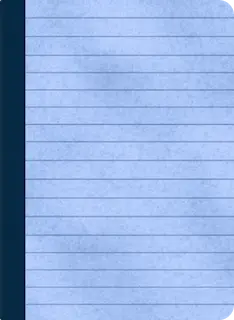

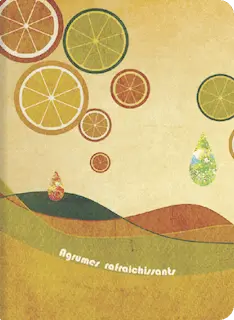
コメント
コメントはまだありません。