✨ 最佳解答 ✨
覚え方とは、記号の覚え方か、日本語での気候区名なのか、分類のしかたなのか、どれでしょうか。それとも、全部ですか?
わかりました。
雨温図はまず、折れ線グラフを見ましょう。
最暖月の平均気温が10°未満だったら寒帯。
そのうち、0°以上だったら「ツンドラ気候」、0°未満だったら「氷雪気候」です。
ツンドラ気候は0°を超えるときと下回るときがあります。
地面が凍り付く時期もあれば、雪が溶けて、こけなどの緑に覆われる時期があって、「ツンデレみたい」と思えば覚えるかも…。
最寒月の平均気温で、熱帯・温帯・亜寒帯を分類します。
最寒月の平均気温が18°以上だったら熱帯、-3°未満だったら亜寒帯、その間だったら温帯です。
問題となっている都市は、境界ギリギリの場合はまずないので、だいたい年中暑かったら熱帯、冬の寒さが厳しくて氷点下だったら亜寒帯だと考えてください。
次に棒グラフ=月別の降水量を見ましょう。
年中雨が少なければ、乾燥帯。
その中でもほとんど雨が降らなければ「砂漠気候」になります。
数ヶ月雨が降る雨季があれば、「ステップ気候」。ステップは草原のことです。
熱帯で年中雨が降れば、密林ができます。これを熱帯雨林というのでこの気候も「熱帯雨林気候」といいます。
熱帯で、乾燥する時期があれば、熱帯の草原で動物たちがいる「サバンナ」になります。だから「サバナ気候」。
温帯は、
大陸の西海岸に多く、偏西風で夏も冬も海洋から風が吹くので、夏は涼しく冬は暖かく、降水量も年中一定量降る「西岸海洋性気候」があります。
一方、地中海沿岸は、夏に乾燥して冬は雨が降るのが特徴です(夏だけ乾燥という特徴は他にはありません)。
地中海沿岸だけでなく、あちこちの大陸西海岸にありますが、地中海沿岸が代表例なので「地中海性気候」といいます。
大陸の東海岸には、日本のように夏高温になり、降水量は年中多い「温暖湿潤気候」と、
冬に降水量が少なく雪もほとんど降らない「温暖冬季少雨気候」があります。
この2つは、名前でどんな気候か分かりますね。
亜寒帯は、年中一定の降水量がある「亜寒帯(冷帯)湿潤気候」と、
冬の降水量が少ない=雪が少ない「亜寒帯(冷帯)冬季少雨気候」があります。
ケッペンの気候区分では、アルファベットを組み合わせて気候区の名前として使っています。
ヨーロッパのあたりの地図を見ると、赤道から北極に向かって熱帯→乾燥帯→温帯→亜寒帯→寒帯と並んでいるので、
ケッペンはそれぞれA・B・C・D・Eと名付けました。
そして、降水量によって、年中降水がある=f、夏に降水が少ない=s、冬に降水が少ない=wを使って、熱帯・温帯・亜寒帯の気候区に使っています。
乾燥帯と寒帯では、
ステップ気候=BS、ツンドラ気候=ETと、ステップ、ツンドラの頭文字を組み合わせました。
氷雪気候=EF、砂漠気候=BWも、FとWは単語(ただし、ドイツ語)の頭文字です。
だから、気候区の分け方を覚えると、気候区の名称(日本語もアルファベットも)や気候の特徴も覚えやすくなると思います。
Csだと温帯で夏に雨が少ない、とかDwは亜寒帯で冬季に少雨だとか。
頑張ってください!
ありがとうございます!!!













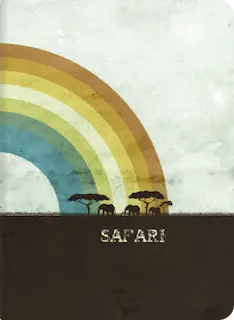


雨温図を見て、どの気候区分なのか日本語も含めて答えられるようになりたいです。