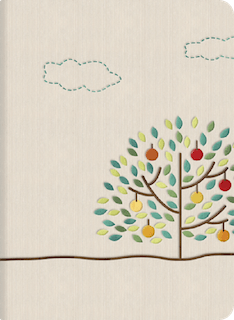5年たっても誰も回答していないんですね・・・
通りすがりの理系高校生さんも大学生になっておられることでしょう。
現在、同じ疑問をもっておられる高校生のために。。。
次亜塩素酸は弱酸なため、一度出来上がるとあまり電離しません。
一方、強塩基の水酸化ナトリウムはほぼ電離します。
したがって大雑把に考えると、
10NaClO + 10H₂O → 10Na⁺ + 10ClO⁻ + 10H⁺ + 10OH⁻
→ 10Na⁺ + 10HClO + 10OH⁻
→ 10Na⁺ + 9HClO + H⁺ + ClO⁻ + 10OH⁻
→ 10Na⁺ + 9HClO + H₂O + ClO⁻ + 9OH⁻
いかがですか?
結果、OH⁻がいっぱい液中に残るので、液性は塩基性(アルカリ性)となるのです。
そしてここから次亜塩素酸(上記では 9HClO)が酸化剤として威力を発揮していきます。
おそらく次亜塩素酸イオン(ClO⁻)も酸化剤として作用できるのではないかな?
ちなみに、水に対する酸解離定数 pKa を見てみると、
フッ化水素酸 HF 2.67
酢酸 CH₃COOH 4.76
炭酸 H₂CO₃ 6.11(pKa1)
次亜塩素酸 HClO 7.53
フェノール C₆H₅OH 9.95
出典:ウィキペディア「次亜塩素酸」および「酸解離定数」、「フェノール」より
いかに次亜塩素酸が弱酸なのか、分かりますね。
あんまり電離しないんです。