✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨
青の蛍光ペンのようにおける理由、
>2つ混じっていて、それぞれ10mL使っているから。
その後のアンモニアの物質量については次式のような表せるのところの式の意味がわかりません。
>左辺は、NH4NO3からは1mol、(NH4)2SO4からは2molNH3ができるから、Zの方を2倍しています。右辺は問4の塩酸molになっています。
この問題はアンモニアと塩酸と水酸化ナトリウムが出てくるため逆滴定であってますか?
>水酸化ナトリウム水溶液は過剰に入れているから、2種類のアンモニア発生物質と塩酸の中和。まあ、逆滴定ではありますが、水酸化ナトリウム水溶液は計算式には入っていません。
これと、硫酸バリウムの沈殿からの式を作り、y,zの連立方程式を解く問題になっています🙇
①それぞれ10ml使ってるというのはどこでわかるのですか?肥料X10gを正確に測りとり、洗浄液も含めて1000mlの試料溶液Aを10ml取ったのとは別ですか?
>その10mLにどちらも入っている。
②問題の流れが私の中で曖昧なのですが、
1.硝酸アンモニウムと硫酸アンモニウムを含む肥料Xがある
2.肥料X10g測りとり純水に溶かした後、洗浄液も加え、1000mlのメスフラスコに移し、これを試料溶液Aとした
3.試料溶液Aからホールピペットを用いて10ml測りとり、過剰量の水酸化ナトリウムを加えた
4.3を加熱するとアンモニア発生したとわかる
5.発生したアンモニアと塩酸反応させ、アンモニウムを全て吸収させた
6.5のうちアンモニアを吸収してない塩酸に水酸化ナトリウムを加え、中和させた。
そして、別の実験として、試料溶液Aから10mlはかり、過剰量の塩化バリウム水溶液を加えると硫酸バリウムの白色沈殿が起こった
と解釈したのですが、
NH4NO3からは1mol、(NH4)2SO4からは2molNH3ができるから、Zの方を2倍するまでは理解できたのですが、1.2✖️10の−3乗はどこから来たのですか?
>上に書いてますが、問4の答えから🙇
教えてくださりありがとうございました🙇♀️
1.2✖️10の−3乗問4の答えを用いるところまでは理解できたのですが、
①上のピンクの蛍光ペンのところなのですが、そもそもなぜアンモニアを求めたのですか?そして、アンモニウムイオンとアンモニアの物質量が1:1だから…に続くのですか??もし、1:1じゃなかった時はどうするのか教えて欲しいです
②その後が頭混乱してしまい、よくわからなかったのですが、
下の方の蛍光ペンの部分で硫酸アンモニウムだけが反応しているのにはわけがあるのですか?硝酸アンモニウムは反応しないのですか?
全体的にどうやってこの問題の答えに導くのかがよくわからなくて、🍇こつぶ🐡さんはこの問題を見てどう導くのか流れ教えて欲しいです🙇♀️
お手数をおかけしてしまいすみませんがお時間がある時に教えていただけると幸いです🙇♀️
上に既に書いたのですが、理解が追いつかないようですね。
①上のピンクの蛍光ペンのところなのですが、そもそもなぜアンモニアを求めたのですか?
>アンモニアと塩酸を中和させているから。
そして、アンモニウムイオンとアンモニアの物質量が1:1だから…に続くのですか??
>それが青とピンクの間の式に続く。
もし、1:1じゃなかった時はどうするのか教えて欲しいです
>1:2なら2倍すればよいし、比で考える。
1:1というのは、NH4+からNH3が1molできることを言っている。
②下の方の蛍光ペンの部分で硫酸アンモニウムだけが反応しているのにはわけがあるのですか?硝酸アンモニウムは反応しないのですか?
>しません。硫酸イオンで沈殿するのは硫酸バリウムだけ。硝酸バリウムだと塩化バリウムで沈殿しない。だからzが求まる。
(i)のy,zを含む式と(ii)のzを含む式からzが求まり、その値を(i)に代入し、yが求まる。
確かに、単純な逆滴定ではないので、解答を見て理解するのが難しい問題かもしれません。
この問題の難しい部分は、実験Ⅰで資料溶液Aをつくり、実験ⅡとⅢで別々にAを10mL使い反応させている。
問4の実験Ⅱが逆滴定で、ここで塩酸molを求め、この値を問5の酸のmolとして(i)と組合せる。実験Ⅲは硫酸バリウム沈殿反応(ii)を作り、(i)(ii)の連立から最終的な比を求める🙇
教えてくださりありがとうございました🙇♀️
手順教えてくださりありがとうございました🙇♀️
実験Ⅰで資料溶液Aをつくり、実験ⅡとⅢで別々にAを10mL使い反応させたのですね…そこがよくわからなかったので助かりました!!
いただいたアドバイスをもとに再度自分で解いてみます!!
本当に何度ありがとうございました😊
読んでも頭で理解しづらい場合は、図示して実験を分けて書いた方が良いです🙇























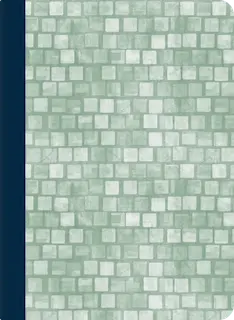
教えてくださりありがとうございました🙇♀️
質問なのですが、
①それぞれ10ml使ってるというのはどこでわかるのですか?肥料X10gを正確に測りとり、洗浄液も含めて1000mlの試料溶液Aを10ml取ったのとは別ですか?
②問題の流れが私の中で曖昧なのですが、
1.硝酸アンモニウムと硫酸アンモニウムを含む肥料Xがある
2.肥料X10g測りとり純水に溶かした後、洗浄液も加え、1000mlのメスフラスコに移し、これを試料溶液Aとした
3.試料溶液Aからホールピペットを用いて10ml測りとり、過剰量の水酸化ナトリウムを加えた
4.3を加熱するとアンモニア発生したとわかる
5.発生したアンモニアと塩酸反応させ、アンモニウムを全て吸収させた
6.5のうちアンモニアを吸収してない塩酸に水酸化ナトリウムを加え、中和させた。
そして、別の実験として、試料溶液Aから10mlはかり、過剰量の塩化バリウム水溶液を加えると硫酸バリウムの白色沈殿が起こった
と解釈したのですが、
NH4NO3からは1mol、(NH4)2SO4からは2molNH3ができるから、Zの方を2倍するまでは理解できたのですが、1.2✖️10の−3乗はどこから来たのですか?
お時間がある時に教えてくださると幸いです🙇♀️