赤で書かれている部分だけ解説します。間違ってたらすみません。
3⑤助動詞
「である」と訳す「なり」は断定の助動詞です。断定の「なり」の上は、必ず体言(名詞)や活用語の連体形になります。今回の場合は、「もの」という体言(名詞)がそれにあたります。
「なり」は断定以外にも、伝聞・推定というものもあります。これは、上が終止形(ラ変動詞は連体形)の場合になります。「なり」の上に何があるかによって断定なのか伝聞・推定なのかを見分けます。
5①ウ②イ
「ば」は非常に重要な文字のひとつです。
順接の仮定条件は、未然形+ば
(~ならば、~たらば)と訳します。
なので、①東の風が吹いたら(吹いたならば)
と訳せると思います。よって答えはウです。
順接の確定条件は、已然形+ば
A原因理由(~ので、~から)
B偶然条件(~と、~たところ)
C恒常条件(~といつも、~と必ず)
という3パターンの訳し方があります。
今回は問題文から原因理由で訳すことが分かるので、②北の風が吹くので(北の風が吹いたから)と訳せると思います。
「~ても」と訳すのは、助詞の「と」「とも」がある時で、逆接の仮定条件になります。
「~と」と訳すのは、助詞の「ば」がある時で、順接の確定条件の偶然条件になります。
4に関しては、動詞の活用という物を覚えましょう。分からなければまた聞いてください。














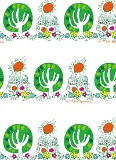

ありがとうございます。助かりました。