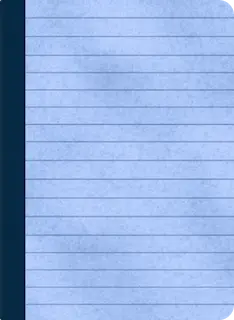_設問文より、「活動時に断層面に沿って2mずれるとする」は認識されていますか?鉛直方向ではありません。鉛直方向に340mずれたことは理解出来ているのですよね?後は、解説文の三角形(右の図)の図で比を確認をしましょう。三角形の比は、1:2:√3、対応する地層は、□:340:xです。□は今回使わないから、計算する必要ありませんね?□は170mになるけれども、計算する必要ありません。
Geoscience
มัธยมปลาย
地学基礎の問題です。
38(2)で下線部の所がわかりません。
解説お願いします🙇♂
38.地殻変動の量●
(1) 1回の地震で平均1m水平方向にずれる断層がある。 この地域では100年に1回の
割合で地震が起こっているとすると,このような状態が10万年続くと, 水平方向の
ずれの量はおよそ何kmになるか。
(2) ある活断層は傾斜 60°の逆断層であり、活動時に
断層面にそって平均2mずれるとする。この活断
層により,現在平地との標高差300mの山が形成
されている。 また,この平地の地下40mの場所
と山頂が60万年前には同一の高さにあったこと
がわかっている。この活断層の平均的な活動間隔
は約何年か。 ただし、この活断層の活動は過去
60万年以上続いているとする。 また, √3= 1.7
とする。
ヒント 100年に1回地震が起こると,10万年では100000÷100=1000(回) 起こる。 〔センター試験 改]
山頂
300 m
活断層
60°
平地
140m
−60万年前 山頂と
同じ高さの場所
38
解説
(1) 1km (2)3000年
(1)100年に1回地震が起こると,10万年では, 100000 100 = 1000 (回) 起こる。
1回のずれが1mなので,1(m)×1000(回)= 1000(m)= 1 (km)
(2) 図1のように,活断層は逆断層なの
山頂
で上盤がずり上がるように動く。この
動きによって、平地の地下40mの場
所と山頂の間に40 + 300 = 340m
の標高差が生じた。 図2で, 活断層に
そう方向のずれを x [m〕 とすると直
角三角形の辺の長さの比より
340 x = √3:2
√3 x = 340×2
活断層は活動時に断層面にそって平均2mずれるので, 400mずれるには,
400 ÷ 2 = 200(回) 活動したことになる。 60万年間で200回活動したので、平均的
な活動間隔は,600000(年) 200(回)=3000(年)
よってx=
300m
ずれの
方向/
活断層
=
680 680
/3 1.7
60°
図 1
=
平地
400
|60万年で
|340mの標高差
140m
-60万年前,
山頂と同じ
高さの場所
12
xm/309
60°
|1|
図2
√3
1340m
คำตอบ
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?
เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉