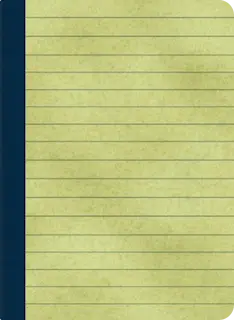ちゃんと質問者さんのいう計算は行われていると思います。例えば、1年生存した個体の中にもこれから9年目や10年目まで生存する個体も含まれています。また、10年目まで生きた6羽は0〜10年目の全ての個体数に含まれるので、足し算するだけで6×11が成立します。それぞれの生存個体にかぶりがあるって事です。回答がかなり変になってしまってすいません…
生物
高校生
生物の質問で写真の問4の平均寿命を求めるときに
階級値×度数/度数の合計をしないでも平均値が出るのはなぜか教えて下さい
310. 生命表と生存曲線 ●表は,ある種の鳥のひな717羽に標識をつけ, 毎年その個体数
作図 計算
を追跡調査した結果である。 ただし, 調査中に調査区域における個体の出入りはなかった
年齢 個体数 死亡数死亡率 (%)
0 717 366
351
126
81
52
33
21
ものとする。
問1. このような表を何
と呼ぶか。
問2.表中の(ア)~ (ウ)の数
値を求めよ。 (ウ)は小数
第2位を四捨五入して
小数第1位まで求めよ。
問3.表をもとに,この
鳥の生存曲線をグラフ
に描け。ただし, グラ
フの個体数は対数値で表せ。を次の語群から選び、
問4 この鳥の平均寿命は, 次の(a)~(d) のうちどれに最も近いか。 ただし, 平均寿命(出生
時点から生存できる年数の平均)は,各年齢の生存数の和を出生数で割った値で求めら
れるものとする。
(a) 1年
(b) 2.5年
2
3
4
144
92
5 59
6
38
7
24
8 15
9
9
10 6
(イ)
9
6
3
G
(c) 4.5年(d) 6年
1000
個体数(対数値)
100
10
1
0
5
年齢
10
2.0000
33÷92×100=35.86...
間4. 出生時点から生存できる年数の平均は,各年齢の生存数の和を出生数で割っ
た値で求められる。
(717+351+225+144+92+59+38+24+15+9+6)÷717=2.34---
回答
疑問は解決しましたか?
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉