✨ ベストアンサー ✨
◯と×の表は、例えば、アルギニン要求株のⅠ型は、遺伝子Aが×、つまり、遺伝子Aに異常があり、遺伝子Bと遺伝子Cは正常ということを表しています。
アルギニンは、20種類あるアミノ酸の1つです。アルギニン(に限らず他のアミノ酸もだが)が無いと、ほとんどのタンパク質を合成できないので、死んでしまいます。
正常な細菌(その書籍では大腸菌かな?)(野生株)は、培地に含まれる前駆物質(もとになる物質)を取り込んで、遺伝子Aから作られる酵素Aによってオルニチンに変化させ、遺伝子Bから作られる酵素Bによってオルニチンをシトルリンに変化させ、遺伝子Cから作られる酵素Cによってシトルリンをアルギニンに変化させてることで、アルギニンを得ています。
なので、これらの3つの遺伝子のどれかが壊れてしまうと、この反応が途中で止まってしまい、アルギニンを得られずに死んでしまいます。しかし、このような変異体でも、アルギニンを始め、他の中間物質を培地に加えてあげれば、生きることができます。これらをアルギニン要求株といいます。作れなくなっても、与えてしまえば良いわけですね。
左側の表の見方ですが、例えばⅢ型。Ⅲ型は、アルギニンで+、シトルリンより左は-になっています。これは、最小培地にアルギニンを加えてあげれば、生育するが、シトルリン他を加えても生育しないという結果を表しています。そして、この結果は、シトルリンを加えても(与えても)生育できないということは、シトルリンをアルギニンに変化させる酵素Cが働いていないからだ、となるわけです。なので、◯×の表で、Ⅲ型の遺伝子Cの下に×が付いています。
同様に、Ⅱ型は、シトルリンより右は+で、オルニチンより左が×になっています。これは、オルニチンを加えても生育しないということは、オルニチンをシトルリンに変化させる酵素Bが働いていないことを示しています。なので、右の◯×の表の遺伝子Bの下に×がついています。
異なる言い方をします。
Ⅰ型の株は、遺伝子Aに×がついているので、酵素Aが働きませんが、BとCは働きます。なので、培地にオルニチンを加えてあげれば、酵素Bによってそれはシトルリンに変化し、酵素Cによってアルギニンに変化するので、生育することができます。なので、左の表では、最小培地に何も加えないと生育せず、-となっていますが、オルニチンより右側の物質を加えると、生育できるので、+となっているわけです。

















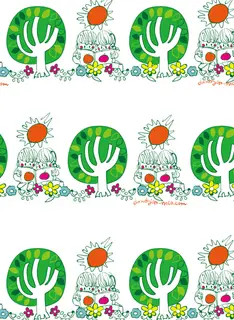



なるほど!!わかりやすかったです!ありがとうございます😊