✨ 最佳解答 ✨
問題を整理します。
実験1:アサリの心臓の心拍数は25回/分
実験2:副交感神経抽出液100mLを100倍希釈すると,アサリの心臓の心拍数は25回/分
実験3:副交感神経抽出液100mLを100倍希釈して,100℃にすると,アサリの心拍数は15回/分
①副交感神経を使用していることから,物質A=アセチルコリン?の実験で,心拍数は減少するはず…。
②実験1でアサリの心拍数は通常時25回/分で,実験2で物質Aを使用しているのになぜ変わらない?実験3で心拍数が15回/分に減少したのはなぜ?
※問3に説明されている物質Xの影響
↳実験2は物質Xで物質Aが分解した可能性
↳実験3は100℃で物質Xが分解したため,物質Aが働けた
∴アサリの心拍数は,通常時25回/分,物質A下では15回/分に減少する
(2)物質Aの影響は,図2のアサリの心拍数が15回/分の時を見れば良い。
↳2/10^2 ng/mL
↳副交感神経1g中の物質Xをx(ng)とすると,実験3では100mLの抽出液をつくってさらに100倍に薄めているので,x/10^4
よって,2/10^2=x/10^4 より,200ng
ちなみに,ngの単位の説明にために1ng=1/10^9(g)と書いてありますが,使いませんね…。



















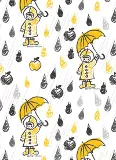



教えてくださりありがとうございました🙇♀️
返信が遅くなってしまいすみません🙇♀️
2つ質問があるのですが、
①たけさんが、教えてくださったところの
『※問3に説明されている物質Xの影響
↳実験2は物質Xで物質Aが分解した可能性
↳実験3は100℃で物質Xが分解したため,物質Aが働けた』の部分なのですが、どうしたら物質Xの働きについてわかるのですか?
上の写真の問3と書かれているところを読んだのですが場所あってますか??
② 2/10^2=x/10^4 ←の部分なのですが、なぜ=になるのですか?
すみませんがお時間がある時に教えていただけると幸いです🙇♀️