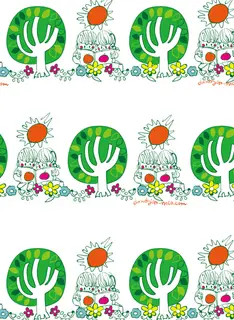Biology
高中
生物基礎です。(5)と(6)は答えを覚えないといけませんか?
問 5. 腎臓における水分の再吸収を促進する
を答えよ。
計算
58. 腎臓の構造と働き ②次の文章を読み、下の各問いに答えよ。
腎臓は、尿を生成し老廃物を排出するとともに体液の量やイオンの濃度を調節してい
腎臓では,まず, 毛細血管が密集した( 1 ) で血液がろ過され, 原尿として(2)
こし出される。 ( 1 ) と( 2 )は合わせて(3)と呼ばれる。 その後, 原尿は
( 4 ), さらにそれに続く集合管へと流れる。この過程で原尿は,必要な成分が再吸
されるとともに, 老廃物が濃縮されて尿がつくられる。(3)と( 4 )は合わせ・
( 5 )と呼ばれる。 表は, 健康なヒトの血しょう, 原尿、尿における各種成分の質量
ーセント濃度(%) を示したものである。 また,腎臓でまったく再吸収も分泌もされない
質であるイヌリンを用いて濃縮率を調べたところ120であった。
問1.文中の空欄に当てはまる最も適切な語を答えよ。
問2. 下線部について, 血液中の成分のうち, 健康なヒトの原尿にはみられない成分の
称を2つ答えよ。 また, その理由について, 10字以内で述べよ。
問3. 表中の成分Eの名称を答えよ。
問4.表中の成分のうち, 濃縮率の最も高い成
分の記号と, その濃縮率を答えよ。
問5.表中の成分のうち, 再吸収される割合が
水に最も近いものの記号を答えよ。
問6.1日の尿量が1.5Lであったとき, 1日
に何Lの血しょうがろ過されたと考えられる
か。イヌリンの濃縮率をもとに計算せよ。
問7.成分Cの1日の再吸収量は何gか。
表
表
成分 血しょう (%)
A
0.03
B
7.2
0.3
0.001
0.1
C
D
E
原尿(%) 尿 (%
0.03
2
0
0.3
0.001
0.1
0
0.34
10.0
0
臓の構造と
問1. (1)一糸球体 (2)一ボーマンのう (3) 一腎小体 (マルビーギ小体)
(4) 一細尿管 (腎細管) (5) -ネフロン(腎単位)
2. 成分一血球, タンパク質
3. グルコース
5. C
理由-こし出されないため
4.D 濃縮率-75
問7.534.9g
201
6.180L
ポイント
問1. 腎臓にはネフロン (腎単位) と呼ばれる構造が多数ある。 ネフロンは,毛細血
管が球状に密集した糸球体とこれを囲むボーマンのうでできている腎小体 (マル
ビーギ小体)とそれから伸びる細尿管からなる。
問2. 血球やタンパク質は, 血管壁とボーマンのうの壁などからなる膜を通り抜け
ることができないためこし出されず.原尿にはみられない。
3. Eは,血しょう中の濃度が0.1%であることや, 原尿には含まれているが尿に
は含まれておらず, すべて再吸収されていることからグルコースであると考えら
れる。
問4.濃縮率は,尿中の濃度血しょう中の濃度で求められる。 それぞれの濃縮率
を求めると,Aは約66.7, B は 0, Cは約1.1, Dは75, Eは0 となる。
問5.水よりも再吸収される割合が低い物質は濃縮率が高くなり, 尿として排出さ
れる量が多くなる。 逆に, 再吸収される割合が高い物質は濃縮率が低くなり尿中
に含まれにくくなる。再吸収される割合が水と同じであれば,濃度は変化せず,
濃縮率は1となる。したがって, 濃縮率が1.1のCが,再吸収される割合が水に最
も近い。
なお,Aは濃縮率が比較的高いことから尿素, Bは原尿にろ過されていないこ
とからタンパク質,Cは再吸収される割合が水とほぼ同じであることからナトリ
ウムイオン, Dは濃縮率が高いことからクレアチニンであると考えられる。
問6.イヌリンはまったく再吸収されないことから,原尿に含まれていた全量が尿
中に含まれている。 濃縮率が120であるということは,濃度が120倍高くなったこ
とを意味している。 含まれているイヌリンの量は変化していないため、 原尿から
水などが再吸収され全体量が120分の1となったと考える。 尿の量が1.5Lであ
ることから,ろ過される血しょうの量は, 1.5L×120で求められる。
問7.原尿 180L ≒ 180000g中に含まれている成分Cの量は, 180000g × (0.3÷100)
で求められる。 同様に, 尿中の量は, 1500g×(0.34÷100) で求められ, この差が
再吸収された量となる。
解答
尚無回答
您的問題解決了嗎?
看了這個問題的人
也有瀏覽這些問題喔😉
推薦筆記
【生物基礎】細胞の構造と働き
9236
49
【生物基礎】要点総まとめ(全単元網羅)
5705
41
【生物基礎】細胞周期と体細胞分裂
5219
21
【受験】*生物基礎*全範囲
4306
6
【生物基礎】顕微鏡/スケッチ/ミクロメーター
3286
13
生物基礎
3282
21
生物基礎バイオーム語呂
1818
21
生物基礎 第1章 I
1536
39
高校1年 生物
1328
21
生物 (遺伝子、DNAなど)
1017
3