✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨
気温が一定に保たれるということは、
その地域が熱平衡にありエネルギー収支がつり合っていることを意味します。
緯度が高くなるにつれて太陽放射の吸収量は減少しますが、
それに比べて地球放射の放出量の緯度差は小さく、
地域によって熱の過不足が生まれます。
これを解消するのが低緯度から高緯度への熱の輸送であり、
潜熱輸送や大気・海洋の大規模な運動によってなされます。
以前の地温勾配についての質問に添付された図から察するに、
浜島書店の地学図表をお持ちですよね。
それの180ページ上部を参照してください。
大気大循環と同様に、海水の循環も低緯度から高緯度への熱の輸送に寄与しています。
海洋表層では風による循環(風成循環)が生まれています。
一方、密度差による鉛直方向の循環(熱塩循環)も存在します。
「海流」という言葉はここでは風成循環を表していると解釈すると、
「大気大循環・海流・熱塩循環によって熱輸送がなされる」
と大雑把ですが説明ができます。
これに詳細な説明を加えれば良いのではないでしょうか。














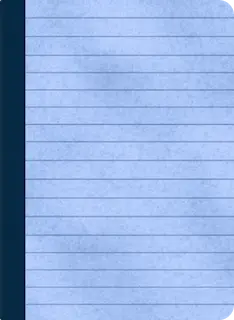


今回質問させていただいたのは、宿題で写真のような問題が出たのですが、なんと答えて良いのかよくわからなかったからです。
教科書を改めて見て、大気大循環による熱輸送で赤道と極の気温差がなくなるのはいいのですが、
残りの、海流と熱塩循環をどのように使えばいいのでしょうか?
もしよりければ教えてください。
前回の質問の写真から教科書が特定されるとは驚きです。