学習とは、なんぞや? 人工知能(AI、ChatGPT)時代に求められる学びとは? 探求学習
12
1258
9
ChatGPTのような人工知能の発達は、まるで、人類の進化の追体験をしているにも感じられます。 人工知能の性能が上がってきたため、私達は、人工知能に負けない知性も身につける必要があると感じています。 ただ、学校での単語暗記中心の一斉授業は、人工知能に、対抗できていないのが現実だと思います。 そこで、脳の刺激(体験学習)がいかに大切かを、まとめてみました。 「主体的・対話的で深い学び」という形式なら、もっと短く、もっと面白く、より個別最適な学びをうながせるのですが、ちせつな文章ですすみません。 興味のある方は、しばしお付き合い下さいな。 ※人類の進化の過程で、声より、文字の活用が歴史的に新しいため、人は、声の方が理解しやすいです。 だから、学校の勉強は教科書中心ゆえ、難しく感じる。 ネット情報も、文字よりyoutubeのような音声と映像の方が、頭に入りやすい。 ※コメントにも同様の内容を書こうと思います。 それを読み上げソフトとか、ブラウザの拡張機能で音声にするのも良いと思います。 例:Read Aloud: テキスト読み上げ音声リーダー
ความคิดเห็น
ล็อกอินเพื่อแสดงความคิดเห็นสมุดโน้ตแนะนำ
คำถามที่เกี่ยวข้องกับโน้ตสรุปนี้
Junior High
技術・家庭
答えをなくしてしまって正解がわかりません、、 教えて欲しいです、!
Junior High
技術・家庭
技術・家庭がいつもひたすら毎日暗記するという 効率の悪い勉強方法で嫌なんです🌀💧 技術・家庭のテスト勉強で効率よく覚えられる 勉強方法などありましたら教えてほしいです🖐🏻
Junior High
技術・家庭
中3技術のエネルギー変換についてです! 思いつかないので案をください。 ちなみに例には (例)①ノートパソコン ②熱エネルギー と書いてありました。
Junior High
技術・家庭
中2技術 2進数と10進数の変換の問題です。 ア、イは10進数に変換でウとエは2進数に変換する問題なのですがわからないのでやり方と答えを教えてほしいです😢
Junior High
技術・家庭
この箱のいい所をアピールしてください! 技術的な考え方でお願いします🙏
Junior High
技術・家庭
ユニバーサルデザインとバリアフリーデザインって何が違うんですか? 教えてくださいm(_ _)m
Junior High
技術・家庭
こんな感じであっていますか?
Junior High
技術・家庭
中二の技術です! 従動軸の回転数の求め方を教えて欲しいです! ベストアンサーさせていただきます🙇♀️
Junior High
技術・家庭
技術の、アクティビティ図とフローチャートの意味を分かりやすく教えれる方教えてください‼️大至急です😿
Junior High
技術・家庭
技術のmicrobit(マイクロビット)についての質問です。 暗くなった+人を感知した時に電気がつくようなプログラムをするにはどのようにすればいいですか?
News














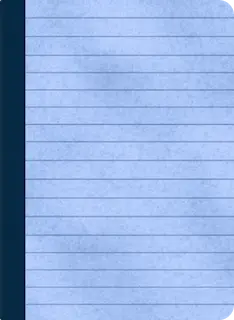




2024.4/25追記
【AI】人工知能の現在を日本はどこまでわかってる?脳科学者・茂木健一郎が講義!
https://www.youtube.com/watch?v=iIouc8g9giw
この動画は、
・人工知能の現状
・人工知能の長所と短所
・人工知能に負けない人間の脳の長所
についての内容です。
2024.3/12追記
人工知能の次の局面?
総合学習の発表原稿を人工知能を作って、棒読みすることができる。
だから、セッション方式(発表中に質疑応答をするので、原稿通りに発表が終わらない、マルチエンディング)の発表なら、人工知能だよりの学習では、対応できない。
故に、学校現場も、そういう授業形態に移行して、人工知能対策をしだしている。
だったのだが、この方式ですら、人工知能は対応してきた。
その結果、株式市場に影響を与えている。
アメリカの番組では、Groqの実力が放送されている。=多くの人が、新しい局面を目の当たりにしている。
終わりました。多分、googleからすぐに消されます。
https://www.youtube.com/watch?v=G0dtYrOZWr0
Nvidiaのライバル?革新的AIチップを開発するGroqについて解説してみた
https://www.youtube.com/watch?v=RgO8Zmc3qyU
2024.1/8追記
【落合陽一:2024年は超AIが来る】超AIとは何か/課長レベルの仕事もできる/一番のネックはGPU/コンサルは不要に/日本以外は雇用が減る/自分データを管理せよ/文書を書かなくなる/キャラ作りが全て
https://www.youtube.com/watch?v=q1BYuqVprnI
【落合陽一:超AI時代の生存戦略】藤井聡太のすごさ/「AI +人間」の伸び幅がデカい/戦争はもっと起きる/怖いのは地震/「動画で学ぶ」から「AIで学ぶ」/生産性は10倍に/マスではないオタク性を極めよ
https://www.youtube.com/watch?v=MJzzsCWgl0U
23.10/7追記
人工知能の進歩が、近未来どのように社会に影響するか考える上で参考になる動画です。
【ロングバージョン】AIを世界一活用する企業に ソフトバンクGの孫氏が講演
https://www.youtube.com/watch?v=Gh0xzbgCIgg
5.求められる学びとは、
①キーワード
○体験を通した学び
○主体的・対話的な学び
○課題発見・課題解決
★結局、文科省の言っていることは、あながち間違いじゃないんですよね。
それを学校で、実施するのは、色々大変なんですけどね。
▲単語の暗記
▲教科書の焼きまわしの一斉授業
②今求められている学習を考える基準
つまり、学習の次元(新しい概念)や質が問われている。
勉強において、質と量は当然大切です。
しかし、それ以上に、次元(新しい概念)が大切です。
時代遅れの勉強だけをいくら質量をあげてこないしても、
新しい次元(新しい概念)で学んだ者には勝てない。
質×量×次元(新しい概念)の総計で勝負が決まります。
WWⅠ~WWⅡの総力戦の世界大戦がその事を証明しています。
③人工知能(プログラム)という技術革新が特異では無い。
さまざまな技術革新が早すぎて、遺伝子による環境適合をする前に、人の生活様式が変わってしまう。
人は、遺伝子では無く、学習によって、生きるすべを学んでいく(学んでいかざるおえない)生物なのです。
④生命の進化は、情報伝達のリレー。
私達、人類も、そのリレーを続けなくてはなりません。
続けるために、生まれた時点で未完成な人は、10代までの学習で、様々な事を学ばなくてはなりません。
人類の知性は、コンピュータを発明し、人工知能をプログラムしました。
道具を発明し、遺伝子に頼らない繁栄をしてきた人類の最後に発明した道具に、人工知能がなるのでしょうか?