石油はまた全然違う話です。
石油のもとになっているのは様々な有機物ですが、多いのは動物プランクトンです。動物プランクトンの死骸や魚の糞、食べ残しが堆積して層を成すのは海底ですよね。海底が地殻変動で海面から表出して地上化する。また地殻変動で海底になる。こういうことを繰り返したり、陸地である時に火山噴火で火山灰が堆積する。河川が氾濫して土砂が堆積する。こうして地層が形成されますね。動物プランクトンなどの有機物が圧力をうけ、変化してできた石油や天然ガスは、地表方向にすなわち上に向かって移動しようとする中で、褶曲運動で作られた背斜構造部の不透水層の下に溜まりやすくて、結果的に長期間地中に眠り続け圧力を受け続けてきたものが現在の埋蔵石油になっています。ですから、地殻変動だの褶曲だのという用語がいくつか出てきましたが、これらは新規造山帯によく見られる現象なので石油は新規造山帯部分に多いというわけです。
専門外ですので荒い説明ないしは誤った部分があるかも知れませんので、自然地理が専門の方、地学方面の方に後を譲ります。お助けください。
回答
マグマの中には様々な物質が溶け込んでいます。噴火とはこうしたマグマが地表面に噴出してくることですね。地表に出る過程で少しずつ冷えていくわけです。あっつあつでドッロドロのマグマの中に溶け込んだ金属は、それぞれが異なる凝固点をもっているわけですから、冷えていく中で順番に凝固していくわけです。例えば鉄の凝固点は1536度、銅の凝固点は1084.5度だそうです。圧力とか周囲の岩石や水との接触の影響もありますからそんなに単純ではありませんがだいたいそういうイメージで、ある金属元素がそこに集まって塊をなす鉱床を作ると理解してください。
すなわち、火山活動が活発な地域にさまざまな金属鉱床が分布している=新規造山帯やそのたのプレート境界部にある
このほか古期造山帯の地域などでも、過去に活発な火山活動がみられたところには鉱床が眠っていてもおかしくはありません。浸食が進んで鉱床が地表に露出すれば、雨水や河川水流などで浸食、運搬されて、下流に堆積して新たな鉱床を作る可能性もあります。川で砂金探しとか、砂場で砂鉄とりとかあるでしょう?あれもそういうヤツです。
かなり単純化して説明しました。理科じゃないのでこんなんで、なるほどーっと納得してもらえたらそれでいいのではないかと思います。
疑問は解決しましたか?
この質問を見ている人は
こちらの質問も見ています😉














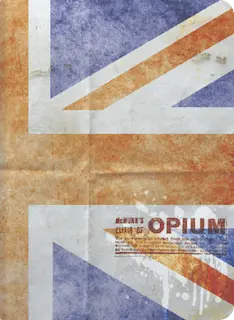



ありがとうございます