✨ ベストアンサー ✨
地図中の、Gのコースで頂上に近いところに「・394」と描かれています。これは標高点といって、この地点の標高を示しています。
こういう点があるということは、三角点のように標高の測量がしやすい=山頂で見晴らしがいいところだと考えられます。
等高線は10m間隔でしか描くことができないので、周りとの高低差が10m未満の場合に、表現できないことがあります。
ここの場合は、少なくとも390mの等高線よりも4m高いので、山頂の可能性があります。
…と、解説を書いた人は考えたんでしょうが、「可能性」なので、調べてみました。
下の図は、地理院地図で標高ごとに色分けしたものです。
地図と標高データにズレがあるようですが、少なくとも、「・394」と描かれたあたりには、頂上はなさそうです。
でも、私は、そこではなくて、電波塔の記号のあたりに小さな頂上があるんじゃないかと考えて、標高ごとの色を塗ってみました。
電波塔は、山の頂上に建てた方が、電波が届きやすいじゃないですか。
で、これも、下の図で描いていますが、Gのコースを登る途中、右手に頂上が見えます。
地図をかなり拡大しているので、頂上と電波塔の記号がズレていますが、標高435m以上440m未満の頂上(等高線では430mと440mの間だから描かれない)が存在することは確かです。







![[図3]はシカゴ物相場の価格の推移を示したものである。近年の穀物価格の高騰が世界の食料事情... - 1](https://d1e9oo257tadp1.cloudfront.net/uploads/qa_question_image/file/1752397/thumb_l_webp_B9A48E68-BC38-4BCE-B08D-B84711BFB89B.webp?Expires=1748164968&Signature=aiui8lFo8J03JFKDu92SgLNa8g-B5OZXCEw9jmQlyfqrpnYz3fdXdhMUBIGp50JgGBgwa9IK3hDeHfuTE-EVVW5dJFVJRxD6d~WEimF0w5hXnYvJ51lbbmJj9wzqXsFASfgfRHeUs5eH-jsVeA~uvGFXD5P~lIpiGH0q68Ckb6OAEPoz-aYzZd9mHkUtwYG0UIOr8yXcQDuF5I3QmtTLRPNvos7oX6iwvK06Xklih-K1-vi3R4xI3xk-hBNnO5vMvW7nKp4v-fptj2mvagtXzliO-AAHqv-lQWinukvBVwIOdAcTn1skMAF--tDpOWimT9imFCzxq11scuT1XffZIA__&Key-Pair-Id=K2W722D70GJS8W&Expires=1748164968&Signature=kwHWd6GT4N~i7U3NWbjja9gJkGqU3zUMOzsd3gNE7kHtrcDnO5~p0fnCdfXfAfqZjgdCj0-jQn74TZFgovscUCiq0Rnuh5U7Ed5-xVW~2L~Ft9xoywdcSvuEQbylPOO-ghB~fCaHIy~N1TghoK5uIuPQtNIbC8FxFHh5bSgu-I3iMpV6rSI9XpLhwMt1tY5yd6zS1qtXjqYKujFGQKvj3vv-LiSK8~VcNtZbtfbGy3zB5ygF9R~z--X2eDcZPzk0mHI-v4kWmAbMB3iBRLuZ~Y-pwtf6HywyA-mXHehSzLpjd1wZSXRndbEptzSJTDQIZ9UI1dDieAWlmynLH1nIbQ__&Key-Pair-Id=K2W722D70GJS8W)







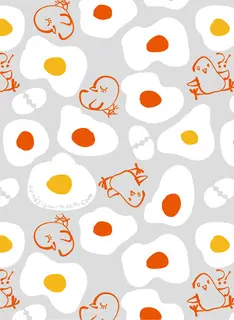




わざわざ調べていただき、とても丁寧に解説ありがとうございます!!🙇♀️🙇♀️🙇♀️