✨ ベストアンサー ✨
この問題の地形図で示されたあたりは氾濫原で、自然堤防と後背湿地があります。
自然堤防は、後背湿地よりも数10㎝~数m標高が高いので、川が氾濫しても水に浸かりにくいので、昔から集落が立地しています。
家を建てるなら、水害にあいやすいところよりも、あいにくいところに建てますよね。
逆に「C」の場所は後背湿地で、水害にあいやすいので家は建ちませんが、低湿地だから水田に適しています。
ちなみに、Dの周りの点線は土地利用の境界です。内側は集落、外側は田、という。
なるほど!!集落が判断の要素になるんですね。分かりやすい説明をありがとうございます🥹


















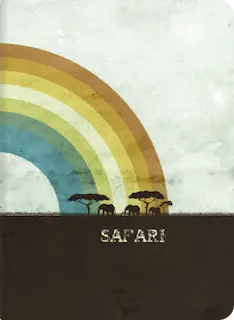





Dの集落はどうして自然堤防上にあると分かるのですか?
という質問については「集落があるから」という答になります。
最近は、後背湿地にも住宅が建っていることがけっこうありますが、その場合は道路が整備されていることで新しい住宅地だとわかります。
でも、ここは、幅の広い道路がない、古くからの集落のようなので、自然堤防だと判断できます。